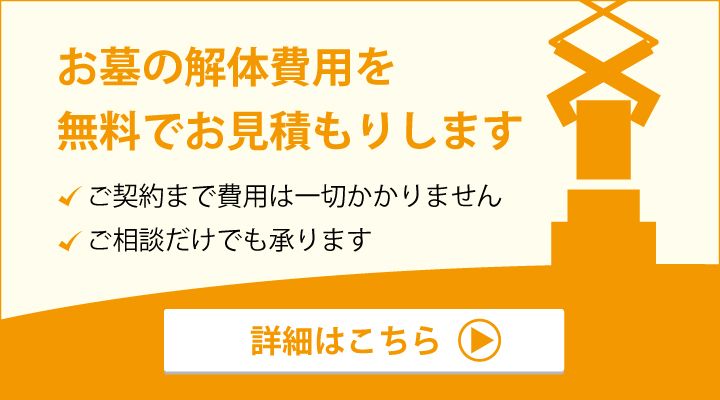墓じまい・永代供養にしたら位牌はどうする?処分や供養の方法と手続き

墓じまいをして遺骨も永代供養にしてこれで一安心と思っている方。
仏壇や位牌はどうしましたか?
お墓、遺骨、仏壇、位牌、いずれも慣習に従えばその内で代々祀っていくものでした。
墓じまいや永代供養をした方は、お仏壇やお位牌についても考えてみてください。
目次
位牌とは何か

そもそも、位牌にはどんな役割があるのでしょうか。
位牌は故人の戒名などを刻む木札
位牌とは、故人の戒名、俗名、享年、没年月日などを刻む木札のことです。
戒名とは仏弟子になったことの証として付けられる名前で、本来は生前に修行をして授かるのが理想です。
しかし、俗名のまま亡くなると故人は極楽浄土に旅立てないということで、亡くなった時に戒名をつける風習が定着しました。
戒名はあの世でも通じる故人の名前で、位牌は故人の名札としての役割があります。
位牌は故人がこの世に来る時の依り代になる
位牌は、故人がこの世に来る時の依り代になります。
葬儀の後は、四十九日までに本位牌を作ります。
本位牌を作った後は「開眼法要」または「魂入れ」などと呼ばれる法要をお仏壇と一緒にします。
位牌は開眼法要をすることで、故人の霊に依り代として認識されるようになります。
故人は自分の依り代を見つけることで、家に帰ってくることができます。
お仏壇に向かう時は故人が帰ってきているかもしれないので、ご挨拶する気持ちでお参りしましょう。
位牌と仏壇
仏壇とは、その宗派で最も大切にされる仏様を祀ってお参りするための施設です。
「家におけるミニチュア版のお寺」という表現をされることもあります。
仏壇がある場合、位牌は仏壇に祀るので、ご先祖様にお参りするための場所という役割もあります。
仏壇と位牌はセットで扱われることもあるので、仏壇の処分を考えるなら位牌のことも同時に考えることになるでしょう。
仏壇の処分は、お寺でお焚き上げをしてもらったり、仏具店に引き取ってもらったりする方法があります。
同時に位牌の処分も考えているなら、お仏壇と一緒に引き取ってもらえるでしょう。
仏壇の供養について、詳しくはこちらをご覧ください。
墓じまい・永代供養にした場合の位牌の扱い方4つ
墓じまいや永代供養をした後の位牌の扱い方は、主に以下の4つがあります。
ここでは、位牌の扱い方について個別に解説します。
1.自宅で保管する
墓じまいや永代供養にしたからといって、早急に位牌も処分をする必要はありません。
位牌を手元に残し、お家でお参りを続けるのもいいでしょう。
ただし、跡継ぎがいなくなるまでには位牌を供養する必要があります。
位牌を自宅に置いておく期限や、先々の供養の方法は念頭に置いた方が良いでしょう。
2.一時的にお寺に預ける
数カ月や数年の単位で、位牌をお寺に預かってもらう方法です。
位牌の処分をすぐに決断できない方や、家に祀る場所がない方はお寺の一時預かりを検討しましょう。
位牌の処分をすぐに決断できない、あるいはすぐに処分したくないけど、家に祀る場所がないという方はお寺の一時預かりを検討しましょう。
3.永代供養にしてもらう
遺骨と同様に、位牌を永代供養してもらうという方法もあります。
まずは、ご遺骨をお願いする永代供養先に、位牌の永代供養もお願いできるか聞いてみましょう。
位牌の永代供養だけで受け付けているお寺もあるので、別で探しても構いません。
一般的に、永代供養された位牌は弔い上げの回忌に達するとお焚き上げされます。
お寺によって年数は異なりますが、三十三回忌や十七回忌などのタイミングで行われます。
4.お焚き上げしてもらう
位牌をお寺にお焚き上げしてもらう方法です。
お焚き上げとは、お寺や神社で祭祀の道具などを供養して焼却することです。
位牌は仏教のものなので、位牌のお焚き上げはお寺に頼みます。
もしお仏壇のお焚き上げも考えていれば、位牌も一緒に供養してもらいましょう。
位牌を供養する費用はどれくらい?
位牌を供養する費用相場は以下の通りです。
なお、費用相場は、地域や宗派によって大きく異なる場合があります。
- 自宅で供養:0円
- お寺の一時預かり:1~3万円/年
- 永代供養:5~50万円/1名(安置期間によって大きく異なる)
- お焚き上げ:1~5万円/1名
この他、位牌を動かしたり処分する際は「魂抜きの法要」のお布施も必要です。
お布施の相場は、1~5万円程度です。
加えて、「御車料」として5千~1万円程度を包むこともあります。
墓じまいから位牌と遺骨を永代供養にする流れと手続き
墓じまいをしてから遺骨と位牌を永代供養にする流れは、以下のようになります。
状況によっては、並行して進めたり、前後しても問題ありません。
墓じまいについて詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。
1.親族やお寺に墓じまいの相談をする
まずは、ご親族や墓地の管理者に墓じまいの相談をしに行きます。
ここで了承を取らずに墓じまいを進めてしまうと、後々のトラブルに繋がる可能性があるので注意しましょう。
2.解体業者を決める
墓じまいをすることが決まったら、お墓の解体を依頼する業者を決めます。
契約する前には、必ず見積もりを取りましょう。
指定業者がいる場合は、お寺や管理者に紹介してもらってください。
指定業者がいなければ、自分で探す必要があります。
近くの石材店に当たったり、ネットの紹介サービスを利用してみましょう。
3.永代供養先を決める
業者に見積もりをお願いしている間、お墓に入っている遺骨の永代供養先を決めます。
永代供養のお墓には、以下のようなものがあります。
合祀墓
永代供養墓の中では、最も費用が抑えられるタイプです。
ただし、他の人の遺骨と混ざってしまうというデメリットがあります。
樹木葬
植栽の下にある納骨室に骨壷のまま納骨するタイプや、土に直接埋葬して自然に還すタイプなどがあります。
自然を感じられる場所に遺骨を納めたい方におすすめです。
納骨堂
ロッカーのような棚に納骨する「ロッカー式」や、仏壇と収骨棚がセットになっている「仏壇式」などがあります。
都心では、お参りの際に遺骨が機械で運ばれてくる「マンション型」も増えてます。
また、ロッカー式や仏壇式の場合は、位牌も置いておけるところもあります。
集合型個別墓
お1人やご夫婦、5名以上で利用できるものなど幅広い種類があります。
ほとんどの場合、承継者が不在になるか、所定の年数が経過すると合祀墓へ改葬されます。
散骨するという方法もある

散骨はお墓を必要としないため、年間管理費がかかりません。
個人で散骨をすると思わぬ事故やトラブルに繋がる可能性があるため、専門の業者に依頼しましょう。
4.お墓のある自治体役所で改葬手続きをする
遺骨の引っ越し先が決まったら、お墓のある自治体の役所で手続きをします。
「改葬許可証」が発行されたら、ご遺骨を動かせるようになります。
5.お墓の閉眼法要をする
改葬の準備が整ったら、お坊さんに閉眼法要をしてもらいます。
閉眼法要とは、お墓から魂を抜くために行う法要です。
閉眼法要は、お世話になっているお寺があればそこにお願いしましょう。
なければ近くの同じ宗派のお寺や、ネットの僧侶派遣サービスを調べてみましょう。
6.遺骨取り出し・解体工事
閉眼供養が終わったら、遺骨を取り出してお墓の解体を業者にお願いします。
墓地を更地にして管理者に返還したら、墓じまいは終わりです。
7.遺骨を改葬先に納骨する
引き取った遺骨を、あらかじめ決めておいた場所に納骨します。
8.位牌を供養する
おさらいになりますが、位牌の扱い方は以下の4つがあります。
位牌を自宅で保管する方以外は、遺骨の永代供養先に依頼できないか確認しましょう。
遺骨の永代供養先で対応できない場合は、自分で新たにお寺を探す必要があります。
供養先を決めるタイミングはいつでも構いません。
遺骨の供養先を決めるタイミングでも良いですし、墓じまい後に決めても良いでしょう。
お墓さがしでは、全国対応でお仏壇の供養・処分費用の無料見積もりができます。
仏壇と一緒に位牌の供養と処分も承ります。
墓じまいに伴う位牌の処分をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
【無料】お問合せ>>

位牌なしでも供養できるのか?
結論をいうと、位牌はなくても供養できますが、結局は遺された方の気持ち次第です。
位牌は、お家で故人にお参りできる場所です。
お参りする場所が明確になっていることで、気持ちが落ち着くという方もいます。
しかし、供養で大事なことは遺された方の気持ちです。
位牌がないとご供養の気持ちが落ち着かないということであれば、位牌の処分はまだ早いかもしれません。
逆に、位牌がなくても故人を思い、供養の気持ちを持てるという方は、位牌はなくてもいいのではないでしょうか。
納得できるご供養の形に位牌は必要ですか?
ご自分の気持ちを確認してみてください。
まとめ
墓じまい後の位牌の扱い方に関して、以下の内容を紹介してきました。
- 跡継ぎがいる場合は、位牌を手元に残しておいても問題ありません。
- 跡継ぎがいない場合は、永代供養やお焚き上げをしましょう。
- 位牌を供養するタイミングに決まりはありません。
- 位牌が無くても故人を供養できますが、必要と感じる方は残しておいても良いでしょう。
墓じまいをしたり遺骨を永代供養にしたからといって、位牌もすぐにどうしなければならないということはありません。
供養しようと思ったタイミングで動き出すのでもいいでしょう。
ご相談・お見積もりも無料で承ります
お墓さがしでは、墓じまいのご相談やお見積もりも無料で承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
墓じまい・永代供養にしたら位牌はどうする?処分や供養の方法と手続きに関する記事
-
墓じまい後の仏壇はどうする?処分の方法と流れ
墓じまいをするということは、広くいうと代々の祭祀を終えたり、祭祀の場所を変えるということになります。もしお墓の他に仏壇がある…
2022年10月28日
-
墓じまいとは?費用と流れを詳しく解説!トラブル対策も紹介
面倒を見ることができないお墓、あるいは、将来的にお世話をする人がいなくなってしまうお墓にお悩みでしょうか?お墓と聞いてイメー…
2024年8月13日
-
永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説
こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…
2025年2月6日
永代供養後の位牌に関するよくある質問
-
遺骨を永代供養した後は、位牌をどのように扱えば良い?
後継ぎがいる場合は、手元で保管しておいても良いでしょう。跡継ぎがいない場合は、お寺に預けたり、永代供養やお焚き上げをしてもらいましょう。
-
墓じまいをしたいけれど、位牌はいつ永代供養すれば良い?
位牌を永代供養するタイミングに決まりはありません。墓じまいをする前や、墓じまい後に行っても良いでしょう。
-
位牌がなくても故人を供養できる?
位牌がなくても故人を供養できます。ただし、お参りする場所が明確になっていることで気持ちが落ち着くという方は、位牌を手元に残しておいても良いでしょう。