永代供養の費用の支払い方法を解説!封筒の書き方は?
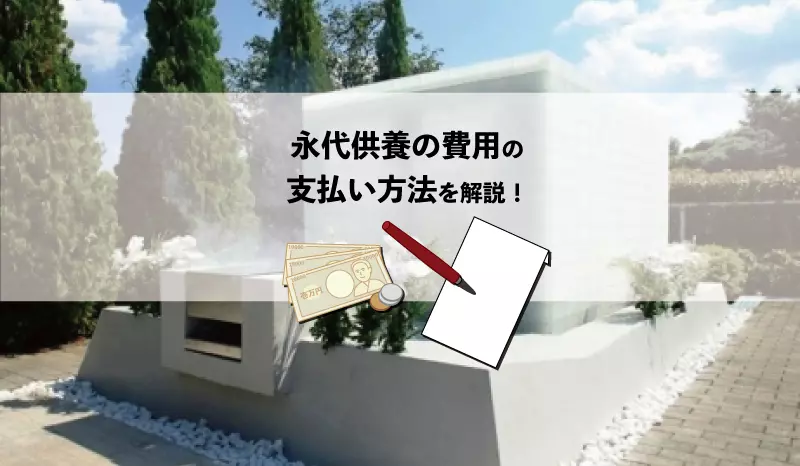
お墓の購入にはお寺が絡む分、やはり普通の買い物よりもマナーなどに気をつけなければならない気がします。
永代供養墓を契約すると、永代供養料を納めます。
銀行振込の場合はそれほど気をつけなくても大丈夫ですが、お寺さんに手渡しをする場合にはやはりいくつか気をつけなければならないことがあります。
今回の記事では、永代供養料を始めとした、永代供養に関する費用の支払い方法を解説します。
なお、永代供養全般については、『永代供養とは?』で解説しています。
また、永代供養の費用について詳しく知りたい方は、『永代供養の費用はどれくらい?』をご覧ください。
目次
永代供養とは
永代供養とは、将来にわたって長い期間故人を供養することです。
近年では、特に「家族や親族に代わって寺院などの墓地管理者が故人を将来にわたって供養すること」を言います。
また、永代供養をしてもらえるお墓を、「永代供養墓」と言います。
永代供養の費用相場と内訳
一般的に、永代供養をしてもらうには、永代供養墓を契約します。
永代供養墓の費用は、3~250万円程度です。
この他、年間管理費が3千~2万円程度かかります。
年間管理費は、かからないこともあります。
永代供養墓には様々な形式のお墓があります。
種類ごとに見る永代供養墓の費用相場は、以下のとおりです。
| 種類 | 合葬(合祀)墓 | 樹木葬 | 納骨堂 | 永代供養付き一般墓 |
| 画像 |  |
 |
 |
 |
| 初期費用 | 3万~30万円 | 5万~100万円 | 10万~250万円 | 80万~200万円 |
| 年間管理費 | 0~3千円 | 0~1万円 | 0~2万円 | 0~2万円 |
| 墓地一覧 | 一覧 >> | 一覧 >> | 一覧 >> | 一覧 >> |
永代供養料
永代供養料とは、お寺などの墓地管理者に永代供養をお願いするための費用です。
永代供養墓の契約時に1回支払います。年間管理料のように毎年少しずつ支払うものではなく、お墓を契約する初期費用として必要です。
永代供養墓の販売価格は、永代供養料を単独で表示するよりも、永代供養料と墓地使用料(、場合によっては彫刻料など)を含めて表示することが一般的です。
(「永代供養料」としてお墓の販売価格を表示する場合も、そこには墓地使用料が含まれていることが多いでしょう。)
年間管理料
永代供養墓を契約した場合も、年間管理料が発生することがあります。
また、本来意味合いが異なる言葉ですが、お墓にかかる年間の維持費を「年間護持会費」という言い方をする墓地もあります。
永代供養墓で年間管理料がかかる場合は、3千~2万円程度です。
なお、年間管理費がかからない、あるいは、一括前納できる墓地では、年間の支払いをしなくて済みます。
その他の費用
この他、納骨時の納骨手数料、納骨法要のお布施、銘板彫刻料などがかかることがあります。
永代供養料の支払い方法
永代供養料の支払い方法は、大きく当日現金手渡しか、銀行振込が考えられます。
手渡しの場合は、現金を封筒に入れて渡します。
手渡し、あるいは振込のタイミングは、契約前の説明に従います。
永代供養料の封筒はどうする?
永代供養料を手渡しで納める場合は、白無地の封筒に現金を入れます。
封筒は、郵便番号の印刷がないものを選びます。
筆は、薄墨ではなく濃い墨のものを使います。
表書きは、中央上半分に「永代供養料」、中央下半分に氏名または家名(「~家」)を書きます。
中袋があれば、表面中央に金額を旧漢字で(金〇〇萬圓也)、裏面右下に住所、氏名、電話番号を記載します。
中袋がなければ、封筒裏面右上に金額、左下に住所、氏名、電話番号を記載します。
なお、浄土真宗の場合は追善供養の考え方が無いので、表書きは「永代経懇志」とします。
永代供養料の渡し方
永代供養料は、ふくさまたは風呂敷から取り出し上に重ねて、相手から見て文字が読める向きで差し出します。
永代供養料はローンで支払える?
墓地や霊園によってはローンで永代供養料を支払うこともできます。
石材店などの民間企業が販売代理店としてお墓を売っている場合、企業独自のローンを用意していることがあります。
また、寺院と提携している銀行で「メモリアルローン」を用意していれば、利用できる可能性があります。
「メモリアルローン」は葬祭やお墓に用途を限るローンで、一般的には審査が通りやすいとされています。
まずは、墓地やお墓の販売代理店に聞いてみましょう。
永代供養墓の年間管理料の支払い方法
年間管理料の支払い方法は、銀行振込、あるいは引き落としが一般的です。
ただし、一部のお寺では、お彼岸などに催される合同法要で手渡したり、檀家総代が集金に来る、ということもあります。
年間管理費(または年間護持会費)がある場合は、契約前に入金方法を確認しましょう。
また、すでにあるお墓の管理料の支払い方法が分からない場合は、お寺や管理事務所などの墓地管理者に問い合わせましょう。
永代供養をした後もお布施は必要?
永代供養にした後でも、お布施が必要になることがあります。
法要をするならお布施は必要
故人を永代供養墓に納骨した後でも、法要をする際にはお布施が必要です。
特に、納骨法要は必須にしている墓地も多く、この場合は納骨の都度お布施が必要です。
また、これとは別に一周忌や三回忌などの年忌法要をする場合も、もちろんお布施が必要です。
ただし、永代供養墓の使用要件に年忌法要を必須とする墓地はそれほど多くはないでしょう。
納骨法要や年忌法要のお布施の相場は、3~5万円程度です。
さらに、僧侶に墓地の外に出向いてもらうような場合は「御車代」が、法要の後の会食に僧侶が出席しない場合は「御膳料」を別途包みます。
いずれも、5千~1万円程度です。交通費がこれを上回る場合、御車代は実費より上のキリのいい金額を包みます。
お布施の封筒と書き方
お布施は、郵便番号欄が印刷されていない白無地の封筒に包みます。
筆は、薄墨ではなく普通の濃い墨のものを使います。
表書きは、中央上段に「御布施」、中央下段に氏名または名字を書きます。
中袋があれば、表面に金額を旧漢字で(金〇〇萬圓也)、裏面右下に住所、氏名、電話番号を書きます。
中袋がなければ、裏面に金額、住所、氏名、電話番号を書きます。
お札は、表書きが見える方から取り出したときに、肖像画が見えるように向きを揃えます。
葬儀の香典では新札は用意していたようで良くないと言われますが、お布施は新札のほうが丁寧です。
お布施を渡すときは、ふくさから取り出し、ふくさの上に封筒が乗っている状態にして、相手から文字が読める向きで差し出します。
まとめ
永代供養の費用には大きく、契約時に支払う永代供養料と、毎年支払う年間管理料があります。
年間管理料は、お墓によってはかからないこともあります。
永代供養料を含めた永代供養墓の初期費用の相場は、3万~250万円程度です。
永代供養料は、銀行振込か直接手渡しで納めることが一般的です。
手渡しにする場合は、白無地の封筒に表書きを「永代供養料」として包みます。
年間管理費は、かかる場合は年間3千~5万円程度です。
基本的には銀行振込や引き落としで納めますが、お寺の慣習によっては、合同法要に持参したり、檀家総代が集金に回ったりしたときに納めます。
この他、法要を営む際にはお布施が必要です。
跡継ぎのいらないお墓をお探しですか?
お墓さがしでは、全国にある永代供養墓を掲載しています。
ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
永代供養の費用の支払い方法を解説!封筒の書き方は?に関する記事
-
永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説
こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…
2025年2月6日
-
永代供養の費用はどれくらい?内訳や相場を解説!
永代供養のお墓は「合祀墓」「樹木葬」「納骨堂」など、様々な種類があります。費用は、永代供養のお墓の種類よって大きく変わります…
2025年2月6日
-
永代供養の費用は誰が払う?いつまで払い続けるの?
永代供養がついているお墓といえば、従来のように墓石を建てるお墓よりも費用を抑えられるイメージがあります。しかしながら、永代供…
2025年2月6日
永代供養墓の費用の支払い方法に関するQ&A
-
永代供養料の費用は誰が支払うのでしょうか?
お墓の契約者が支払います。一般的には、納骨される本人または、主に遺骨の供養をする人が契約者になります。これとは別に、家族や親族に費用負担をお願いすることもできます。
-
永代供養料の封筒の書き方を教えてください。
表書きは中央上段に「永代供養料」(浄土真宗の場合は「永代経懇志」)、中央下段に氏名または家名を書きます。中袋がある場合は面に金額を旧漢字で(金〇〇萬圓也)、裏に住所、氏名、電話番号を書きます。中袋がなければ、封筒裏面右上に金額、左下に住所、氏名、電話番号を記載します。

経歴
2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。