公営墓地とは?費用や申し込み方法を解説!民営霊園や寺院墓地との違い
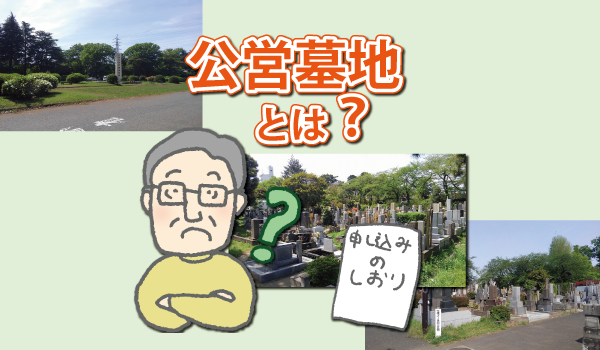
公営墓地は、経営が安定していることや、墓地使用料と管理料が安いことで人気があります。
しかしながら、その人気の高さから墓地の使用者は抽選で決める場合があり、必ずしも公営墓地を使用できるとは限りません。
この記事では、公営墓地について解説します。
なお、その他の種類の墓地については、『墓地の種類を解説!』で解説しています。
目次
公営墓地とは

公営墓地とは、地方公共団体が経営主体となっている墓地のことを言います。
言い換えれば、都道府県や、市区町村が墓地の経営主体になっている墓地です。
都立霊園や県立霊園、市営墓地などがこれに当たります。
公営墓地は厚労省が推奨する形態
公営墓地は、以下のように、厚生労働省が最も推奨する墓地形態です。
これは、永続性、非営利性の観点から、営利団体が経営主体となるべきではないという考え方に基づきます。
墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。
参考:墓地経営・管理の指針等について
実際の公営墓地の管理・運営
実際の管理・運営については、以下の3つのパターンがあります。
公営墓地の管理・運営のパターン
- 地方公共団体が直接管理・運営をする
- 管理・運営を自治体が指定した管理業者に委託する
- 地域の墓地管理委員会が管理・運営をする(共同墓地から移行した墓地)
3つ目の、地域の墓地管理委員会が管理している公営墓地は、もともと昔から地域にあった共同墓地を、後に自治体の管轄に入れたものです。
いわゆる公営墓地・公営霊園のイメージに当てはまるのは、前の2つでしょう。
公営墓地の5つの特徴
公営墓地の5つの特徴をご紹介します。
公営墓地の5つの特徴
- 面積あたりの墓地使用料や管理料が安い
- 申し込み資格に制限がある
- 申し込みに募集期間が設けて抽選することが多い
- 宗教の制限がない
- 石材店の指定がない
1.面積あたりの墓地使用料や管理料が安い
公営墓地では、面積当たりの墓地使用料が安く設定されています。
ただし、都立霊園などの一部の例外は除きます(都立青山霊園では、一区画あたり約400万~1000万円と、その他の墓地に比べてかなり高額です。)。
年間管理料は場所を問わず、その他の墓地に比べて低めに設定されます。
墓地使用料とは、墓所を使用できる権利を得るための費用です。
民営霊園や寺院墓地では、「永代使用料(えいたいしようりょう)」という言い方が一般的です。
区画面積自体は広い傾向にある
ここで、公営墓地では、民営霊園や寺院墓地などに比べて、一区画の面積が広いことに注意が必要です。
公営墓地は面積あたりの使用料が安くても、面積が広いため、一区画の使用料としては、民営霊園や寺院墓地の小さな区画を買った方が抑えられることもあります。
加えて、石材費や工事費用も区画が広いほど高くなるので、総額で見ると、その他の墓地より高くなることもあります。
2.申し込み資格に制限がある
公営墓地には、以下のような要件が設けられていることがあります。
公営墓地でよく見られる募集要件
- 墓地がある自治体に居住している(または本籍がある)
- 埋蔵あるいは埋葬していない親族の遺骨を所持している
- 自治体の中にある他の公営墓地にお墓を持っていない
- 3年以内に墓標を設置することができる
公営墓地は、基本的にその地方自治体に居住している人の生活環境整備のために運営されているものです。
そのため、多くの公営墓地では居住要件を設けています。
さらに、生前購入不可、すでに持っているお墓の引っ越し不可、という要件を設けている場合もあります。これは、より緊急性が高い人に優先して墓所を割り当てるために設けられる要件です。
3.申し込みに募集期間を設けて抽選することが多い
多くの公営墓地では、決まった期間でしか墓地使用者の募集を行っていません。
募集期間は自治体の広報誌やHP上で発表され、その期間内に使用の申込をします。
墓地の募集は年に1回など定期的にしている自治体もあれば、返還区画が一定数に達し次第など不定期で行う自治体もあります。
返還墓所のみの募集も多い
歴史の長い公営墓地ではすでに全ての区画が埋まっており、墓じまいをして返還された墓所のみ募集を行っていることがあります。
抽選で使用者を決めることも多い
公営墓地は、自治体が運営している安心感や、費用の安さなどから人気があります。
そのため、随時使用者を募集するほどの墓所の供給がなく、募集期間を設けて、抽選で使用者を決めます。
加えて、都市部などの人気の墓所では倍率が10倍以上になることもあり、必ず墓所を使用できるとは限りません。
一方、新規造成された墓地や、人口が少ない地域では、使用者を随時募集していることもあります。
4.宗教の制限がない
公営墓地は、自治体が運営する墓地です。公共機関は宗教を選ぶことができないため、墓地の使用にも宗教の制限はありません。
仏教徒のみならず、神道、キリスト教徒、新宗教の方、あるいは無宗教の方など、どなたでも使用できます。
継承不要のお墓も「供養」はされない
「供養」は仏教の概念なので、自治体が主導してこれを行うことはありません。
例えば、寺院や民営の永代供養墓と異なり、公営の合葬墓や樹木葬に埋葬された場合も、その後に自治体が僧侶を呼んで読経するということはありません。
継承不要のお墓に入った後も、お経をあげられたくないという方は、公営の継承不要のお墓がおすすめです。
5.石材店の指定がない
公営墓地でお墓を建てる場合は、石材店を自由に選ぶことができます。
民営霊園や多くの寺院墓地が決まった石材店でしか工事できないのに対して、公営墓地の場合は、1つの業者を指定すると公平性に反する危険性があるため、1つの石材店を指定するということはあまりありません。
相見積もりもできる
石材店に何社か声をかけて、複数社から見積もりをもらうこと(相見積り)もできます。
予算のみならず、石材店ごとの対応面やアフターサービス、信頼度などを比較して、自分で納得できる石材店を選ぶことができます。
公営墓地でお墓を持つ場合の費用
公営墓地でお墓を持つ費用は、立地や広さによって大きく差が出ます。
費用相場は、一般墓の費用相場である100~250万円程度が目安になるでしょう。
年間管理料の相場は、1,000~5,000円程度です。
墓地使用料は立地で差が出る
墓地を持つ費用の内訳は、墓地使用料(永代使用料)、墓石費用、工事費です。
公営墓地の費用に差が出るのは特に墓地使用料です。
公営墓地と言っても、立地によって墓地使用料には大きな差が出ます。
たとえば東京都の運営する公営墓地では、以下のように墓地使用料に差があります。
都立霊園の墓地使用料の例
- 青山霊園 275万円/1㎡
- 谷中霊園 178万円/1㎡
- 八柱霊園 20万円 /1㎡
- 小平霊園 85万円/1㎡
もしも公営墓地に応募する場合は、近隣のほかの民営墓地と永代使用料を比較して検討したほうが良いでしょう。
公営墓地以外で費用を抑えて建墓する方法
比較的安価にお墓を建てることができるという理由で公営墓地を希望する方もいますが、公営墓地以外でも、安くお墓を持つ方法があります。
お墓を安く持つ方法には、以下のようなものがあります。
公営墓地以外で費用を抑えて建墓する方法
- 郊外の墓地を探す
- 小さいサイズの区画を取得する
- 墓のデザインをシンプルにする
郊外の墓地を探す
墓地の種類にかかわらず、郊外に行けば行くほど、墓地の使用料や管理料は安くなります。
お墓参りの頻度にこだわらなければ、多少遠くても郊外でお墓を立てれば、費用を抑えることができます。
小さいサイズの区画を取得する
区画のサイズが小さければ、比例して墓地の使用料や管理料は安くなります。
また、区画が小さければ使用する石材の量も少なくなるので、石材・工事費も抑えられます。
広さにこだわらなければ、小さな区画を用意している霊園を探すのも一つです。
公営墓地の区画は広い場合も多く、結果的には同じ立地でも民営霊園の方が安くお墓を建てられることもあります。
場所によっては、総額100万円以下でお墓を建てられることも珍しくありません。
お墓のデザインをシンプルにする
お墓の形や彫刻が複雑であればあるほど、石材の加工のために費用が掛かります。
お墓のデザインはできるだけシンプルにしましょう。
また、使用する石材の量から、和型よりも洋型のお墓の方が、費用を抑えられる傾向にあります。
公営墓地の申し込み方法
公営墓地の使用を申し込む方法を解説します。
細かい申し込み方法は自治体によって異なるので、まずは自治体の役所に確認しましょう。
1.自治体役所やHPで募集状況と募集要件を確認する
まずは、使用したいと考えている墓地の募集状況を確認しましょう。
墓地の募集状況は、自治体のホームページや広報などで確認できることがあります。
募集状況がHP上で確認できない場合は、墓地を管理する自治体の役所に電話をしてみましょう。「(市営の)墓地について」と伝えれば、担当に繋いでもらえます。
募集状況を確認する際は、あわせて募集要件も確認しましょう。
その自治体に住んでいる年数や、遺骨についての条件が設けられていることがあります。
募集要件を満たさなければその公営墓地を使用することはできないので、他の墓地を検討します。
2.自治体役所や霊園管理事務所で申込用紙をもらう
自治体の役所や霊園の管理事務所で、墓地の申し込み用紙をもらいます。
自治体によっては、ホームページから申し込むことができることもあります。
申込みのしおりなどを発行している場合は、しおりと申込用紙が一緒になっていることがあります。
3.申し込み用紙を郵送して応募する
申し込み用紙に記入して、指定されている場所に郵送します。
申し込み期間が定められている場合は、必ず期限内に送ってください。
これで申し込みが完了です。抽選の結果を待ちましょう。
自治体によっては、ホームページ上のフォーマットを入力することで、申込みを完了できる所もあります。
公営墓地でお墓を建てる流れ
公営墓地でお墓を建てる場合の、一般的な流れを説明します。
1.自治体が告知する募集期間に応募する
墓地のある自治体から、墓地の募集を実施する場合は、募集の告知がなされます。
告知は、自治体の広報誌やHP上で発表されます。
発表された募集期間内に、墓地使用の申込書を提出します。
なお、随時募集している公営墓地についてはこの限りではありません。
申込書は、多くの場合で自治体役所や公営墓地の管理事務所で配布されます。
あるいは、自治体によってはHP上で申し込むことができます。
2.抽選に受かる
募集が締め切られた後、1~数か月後に抽選発表があります。
抽選に受かったら、墓地を使用することができます。
抽選に落ちた場合は、今回の募集はあきらめなければなりません。
次回の募集に再度申し込むか、他の民営墓地や寺院墓地を検討しましょう。
3.資格審査を受ける
抽選に受かった後は、墓地使用者としての資格審査を受けます。
書類などで自治体から指示があるので、それに従います。
4.永代使用料と管理費を納め、使用許可証を発行してもらう
資格審査を通過した後、永代使用料と管理費を納めます。
必要な費用を納めたのち、使用許可証を発行してもらえます。
ここではじめて墓所を使用できるようになります。
5.石材店を決定する
墓地が使用できるようになったら、墓石を建てる石材店を決めます。
契約前に必ず見積もりを取りましょう。
公営墓地では自由に石材店を決めることができます。
公営墓地周辺にある石材店をあたったり、インターネットで調べて石材店を絞ってみましょう。
相見積もりもできるので、1社で納得できない場合は2~3社から見積もりを取ってもらいましょう。
納得のいく石材材店が見つかったら、契約します。
6.工事・引き渡し
石材店に工事をしてもらいます。墓石工事は、通常2~3か月かかります。
工事が終わったら引き渡しとなり、公営墓地での建墓が完了します。
公営墓地のメリット4つ

公営墓地にお墓を持つメリットは何でしょうか。
公営墓地のメリットを4つご紹介します。
1.経営主体の倒産や廃寺の心配がない
公営墓地は自治体が経営する墓地なので、経営主体の倒産や廃寺の心配がありません。
墓地の設置には厳しい審査があるため、通常は経営主体が倒産したり、管理しているお寺がなくなるということは簡単には起こりませんが、経営主体が倒産したり廃寺になったりという事例はないわけではありません。
2.年間管理費が安い
公営墓地では、年間管理費が安く設定されています。
年間管理費はおおむね1,000~5,000円程度に収まることが多く、他の墓地に比べると相場はかなり低い傾向にあります。
3.宗教に関係なく墓所を使用できる
公営墓地は、宗教や信心に関係なく使用することができます。
神道、キリスト教徒、新宗教、無宗教の方などどなたでも使用できます。
加えて、家族間で宗教や宗派が異なる場合も、同じお墓に入ることができます。
4.石材店の指定がない
公営墓地には指定石材店がないので、石材店を好きに選ぶことができます。
複数の石材店から見積もりをもらって比較検討できるので、より良く、よりお値打ちな石材店を探して工事をお願いすることができます。
また、親戚や知り合いの石材店にお願いしたいという場合も、公営墓地がおすすめです。
公営墓地のデメリット4つ

これに対してデメリットは何でしょうか。
1.募集要件を満たさないと使用できない
公営墓地には、多くの場合で居住要件があります。
具体的には、墓地を運営する自治体に一定期間居住していること、また本籍があること、などが挙げられます。
したがって、一部の公営墓地を除き、隣接する自治体の公営墓地を使用することは現実的ではありません。
さらに、居住要件の他にも、遺骨をすでに所持していること、改葬遺骨でないこと、墓碑を3年以内に建てられること、などの要件が加わる場合もあります。
2.常に使用を申し込めるわけではない
一部を除き、多くの公営墓地は使用者の募集期間を限定しています。
募集の頻度は自治体によって様々で、1年に2回、1年に1回、数年に1回、あるいは不定期で募集されます。
また、募集の後に抽選があり、抽選の後は使用許可証の発行というプロセスを踏むため、墓地を使用できることになったとしても、すぐにお墓を建てることはできません。
できるだけ早くお墓を建てたいという方には、おすすめできません。
なお、一部の公営墓地では随時使用者を募集している場合もあり、この場合はその他の墓地と同じスピード感で工事に着手できます。
3.募集に申し込んでも必ずしも使用できない
公営墓地で随時墓地使用者を募集している所は少数で、多くの場合は定期、あるいは不定期に実施される抽選で使用者を決定します。
都市部などの人気の墓地では特に倍率が高く、3年にわたって抽選に落ち続けるということも珍しくありません。
できるだけ早くお墓を建てたい方は、民営霊園などの他の墓地も同時に検討することをおすすめします。
4.お墓にペットと一緒に入ることはできない
2021年4月現在、ペットと一緒に入れる公営墓地はありません。
ペットと共に眠れるお墓を建てたい方は、民営霊園や寺院墓地で検討しなければなりません。
公営墓地に永代供養墓はある?
公営墓地には、最近増えている「永代供養墓」はあるのでしょうか。
永代供養墓とは?

永代供養墓とは、家族や親族に代わり、墓地の管理者である寺院などが、お墓のお世話や供養をしてくれるお墓のことです。
お墓の跡継ぎがいなくてもお墓を持つことができるので、家墓に入りたくない人や墓守がいない人などに選ばれています。
具体的な供養の内容は、年に1~数回ある合同法要での読経などがあります。
従来のような墓石のお墓に永代供養が付いていることはまだ珍しく、永代供養墓の形式としては、合葬墓、樹木葬、納骨堂、その他集合個別墓
などが挙げられます。
厳密には公営の永代供養墓はない
厳密に言うと、公営墓地に「永代供養墓」はありません。
供養とは、仏教上の宗教行為です。永代「供養」墓と言った場合は、読経などの供養が付属します。
地方公共団体は特定の宗教を選ぶことはできないので、公営のお墓に入っている人のために僧侶に読経してもらうということもできません。
そのため、公営墓地には永代供養墓がありません。
ただし、公営墓地の管理者がお墓を管理することはできるので、継承不要の合葬墓や樹木葬などを設けている場合はあります。
公営の継承不要のお墓はある

公営の墓地でも、継承不要のお墓を設置している所は数多くあります。
公営の継承不要のお墓には、以下のようなものがあります。
公営の継承不要のお墓の例
- 合葬墓(合葬型埋蔵施設など)
- 樹木葬(樹木型埋蔵施設など)
- 集合個別式のお墓(立体埋蔵施設など)
これらのお墓は、個人や夫婦、親子、兄弟など、1~数代限りで利用できます。
お墓自体は墓地の管理者が手入れしてくれるので、荒れてしまうことはありません。
供養は必要ないという方は、公営の継承不要のお墓を検討しても良いでしょう。
もっと言えば、読経はされたくないけど跡継ぎがいないという方は、公営の継承不要のお墓がおすすめです。
公営の納骨堂は「預かり」が基本

公営の納骨堂は、基本的に「一時預かり」の施設として用いられます。
したがって、原則一定期間が過ぎた後は、遺骨は親族で引き取る必要があり、寺院などで運営している永代供養付きの納骨堂の代わりに使うことは難しいでしょう。
ただし、一部の自治体では預骨期間を過ぎたのちは合葬墓に改葬してくれる場合もあり、この場合は寺院などの納骨堂に近い使い勝手になります。
期間後の遺骨の対応を、自治体に問い合わせてみてもいいでしょう。
公営墓地と寺院墓地・民営霊園・共同墓地の違い
墓地には、公営墓地以外にもいくつか種類があります。
公営墓地は、他の墓地とどのような違いがあるでしょうか。
公営墓地以外の墓地の種類
墓地の種類は、墓地の経営主体や形態によって分けられることができます。
公営墓地の他の墓地の種類には、以下のようなものがあります。
- 寺院墓地
- 民営霊園
- 共同墓地
寺院墓地と公営墓地の違い

寺院墓地と公営墓地との違い
- 原則同じ宗派の人々で使用する
- 原則寺の檀家になる必要がある
- 空きがあれば随時申し込める
- 仏事の相談ができる
寺院墓地とは、寺院が宗教活動として経営している墓地です。
ほとんどの場合で、寺院の境内にあります。
宗教活動として経営するからには、通常墓地の使用者にも宗教の制限があります。
ベーシックな寺院墓地では、経営するお寺と同じ宗派の人だけがお墓を使用することができ、お墓を使用する人は、お寺の檀家になります。
檀家になると、お墓の他、法事や葬儀などの一切の仏事をお寺にお願いすることになります。
また、お寺によっては合同法要の参加や、毎年あるいは随時の寄付が必要になります。
ただ、最近では使用者の宗教にこだわらないお寺も増えており、在来仏教であれば宗旨宗派不問、あるいは宗教自由という墓地もあります。
特に樹木葬や納骨堂などの継承不要のお墓では宗教を縛らない場合が多く、この場合は檀家などの付き合いも発生しません。
いずれの場合も、お墓だけでなく仏事全般をお願いすることができるので、幅広く相談できる安心感があります。
民営霊園と公営墓地の違い

民営霊園と公営墓地との違い
- 設備やサービスが充実している
- 管理料は高めの傾向にある
- 空きがあれば随時申し込める
- 墓所の種類が多様
- 指定石材店がある
民営霊園は、宗教法人や公益財団法人が経営主体となり、管理を民間団体が請け負う霊園です。
民営霊園では、公営霊園に比べて設備やサービスを充実させている所が多くあります。
美しい景観や快適さを重視し、ガーデニング墓地や欧風霊園などの様々なコンセプトの墓地が誕生しています。樹木葬などの他にも多様な種類の永代供養墓も登場してします。
サービスや手入れが充実している分、年間管理費は公営墓地に比べてやや高めです。
また、ほとんどの場合で民営霊園には指定石材店がついており、必ずしも希望の石材店に工事を依頼することができません。
寺院墓地と比べると宗教の縛りがなく、公営墓地と比べるとすぐに墓地を使用できるため、民営霊園はごく一般的に選ばれるようになってきました。
共同墓地と公営墓地の違い

共同墓地と公営墓地との違い
- 地域の墓地管理委員会が管理・運営している
- 設備面では不便な傾向
- 一般的には周辺の住民が使う
- 空きがあれば随時申し込める場合が多い
共同墓地とは、地域で管理・運営している墓地のことです。
共同墓地は、墓地埋葬法が施行された昭和23年よりも前から集落、村落など地域のコミュニティによって使用、管理、運営されていた墓地です。
その性質上、充実した設備を積極的に取り入れることはしないため、使い勝手は公営墓地に比べると不便な場合が多いです。
また、通常は周辺住民によって使用されます。
公営墓地とは違い、募集期間などを設けることはありません。
空き区画があれば墓地使用を申し込むことができます。
なお、共同墓地の管理を自治体が請け負うようになり、共同墓地であったものが公営墓地になることもあります。
公営墓地で墓じまいをするには

墓じまいとは、今あるお墓を解体・撤去し、墓所を管理者に返還することを言います。
公営墓地で墓じまいをする場合、何をすればいいかを解説します。
1.まずは親族に相談しましょう
墓じまいにを決めてしまう前に、まずは親族に相談しましょう。
また、自分ではない人が墓地の名義人になっている場合は、手続き上その人の承諾書が必要になります。
お墓は一族に関わる問題なので、後々のトラブルを避けるためにも、事前に承諾を取り付けておきましょう。
もしかすると、相談することでお墓を引き継いでくれる人が見つかるかもしれません。
2.遺骨の新しい引っ越しを決める
墓じまいをするにあたっては、遺骨を取り出す必要があります。
遺骨を取り出した後の引越し先を決めておきましょう。
自治体によっては、手続きの際に引っ越し先の受入れ証明書や、所在地などの情報が必要になります。
遺骨の引越し先としては、以下のようなものが考えられます。
- 近くの墓石のお墓
- 合葬墓や樹木葬、納骨堂などの永代供養墓
- 散骨
- 自宅安置
お墓探しでは、全国のお墓や永代供養墓をご紹介しています。
ご遺骨の引越し先でお悩みの方は、ぜひ一度ご利用ください。
3.見積もりを取って墓石を解体する業者を決める
墓石を解体する石材店を決めます。
業者選びは、遺骨の引越し先を探すことと同時に進めて構いません。
業者を決める際は、契約をする前に必ず現地で見積りを取ってもらいます。
見積もりは、正確な位置を伝えられれば立ち合いなしでも取ってもらえます。
公営墓地では、工事をする石材店は自由に選べます。
複数社で見積りを取る相見積もりもできます。
一度取った見積もりに不満があれば、別の会社にも見積もりをお願いしてみましょう。
お墓さがしでは墓じまいの無料見積りも承っています。
墓じまいでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
4.お墓のある自治体役所で手続きをする
お墓のある自治体役所で手続きをします。
遠方に住んでいる場合は、郵送で手続きをしてもおおむね対応してもらえます。
郵送での手続きを希望する場合は、事前に役所の担当者に電話をしておきましょう。
手続きの内容は、以下の2つです。
- 墓地の返還手続き
- 改葬許可申請
墓地の返還手続き
墓地の返還手続きは、墓地を管理している自治体役所でできます。
もし、管理事務所で手続きするように指示があれば、従ってください。
手続き用の用紙をもらえるので、記入して提出します。
改葬許可申請
改葬許可申請は、遺骨の移動のために必要な行政手続きです。
原則、改葬許可を得ないで遺骨を移動することはできません。遺骨は、改葬許可が交付されてから取り出してください。
ただし、遺骨を散骨したり自宅安置する場合は、改葬許可が要らないこともあります。
役所で確認しましょう。
改葬許可申請の記入用紙は、自治体によって異なりますが、記入項目には以下のような内容があります。
- 許可申請をする人の情報
- 被葬者(納骨されている人)全ての氏名、続柄、没年月日、火葬場
- 改葬先(遺骨の引越し先)
- 工事を担当する業者
大体の役所では、分からないところは「不明」でも受理してもらえます。
また、被葬者について分からない場合は、霊園の管理事務所に問い合わせれば情報を教えてくれます。
これらに加えて、「墓地管理者の署名・捺印」が必要ですが、ほとんどの場合、これが役所で処理してもらえます。
あわせて、以下の書類が必要な場合があります。
自治体によりますので、必ずしも必要ではありません。
- 改葬許可申請者の身分証明書
- 改葬先の受入れ証明書または契約書
- 墓地名義人の承諾書(申請者と名義人が違う場合必要)
手続きが完了したら改葬許可証が交付されます。
以降、遺骨の取り出しや解体工事ができるようになります。
5.魂抜きの法要(閉眼供養)をする
遺骨を取り出す前に、「閉眼供養」(魂抜き)をします。
閉眼供養は、墓石を礼拝の対象からただの石に戻すための儀式で、墓前に僧侶を招いて行います。仏教徒でない方は、信仰する宗教に則り、これに相当する儀式を行います。
閉眼供養は必ずしも必要ではありませんが、多くの石材店は閉眼供養を終えていないお墓の解体は受付けていないのが現状です。
基本的には閉眼供養はすることになるでしょう。
6.遺骨を取り出して墓石の解体工事をしてもらう
石材店に遺骨を取り出してもらい、墓石の解体工事を行います。
基本的には、現地に遺骨を引き取りに行きます。
ただし、地域性によりますが、遠方に住んでいる場合は、石材店に依頼して、改葬先に遺骨を送ってもらえるかもしれません。
遺骨を取り出したら、石材店がそのまま墓石の解体工事をします。
墓地を更地にして、管理者に返還します。
7.遺骨を新しい納骨先に納める
遺骨を、あらかじめ決めておいた引っ越し先に納めます。
これで、墓じまいが完了です。
まとめ
メリットの多い公営墓地ですが、しかし応募する上で制限がある点や、競争率が高い点などのデメリットもあります。
ですから墓地を探している時には、公営墓地と寺院墓地、民営墓地を、費用だけではなく、利用する上での様々な面も考慮して比較検討しましょう。
墓地や霊園をお探しですか?
お墓さがしでは、全国の墓地や霊園をご案内しています。
ご希望のエリアや条件に絞ってお探しできるので、ご自分の条件にあるお墓にはどんなものがあるか、一度チェックしてみましょう。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
公営墓地とは?費用や申し込み方法を解説!民営霊園や寺院墓地との違いに関する記事
-
【最新版】2025年度(令和7年度)都立霊園の募集と申込時期は?費用や2024年度の倍率も解説
令和7年度(2025年度)の都立霊園の募集は、以下の通りです。令和7年6月13日(金)~7月4日(金)都立霊園は、東京都が…
2025年7月3日
-
お墓の見積もりはどうやる?墓石と石材店を選ぶポイント
※記事の概要は、こちらの動画をご覧ください。公営墓地に墓地を取得できたら、多くの自治体では1~3年以内にお墓を建てる必要があ…
2024年6月3日
-
【写真付き】お墓の種類を解説!墓地・霊園の特徴とメリット・デメリット
現在のお墓には、様々な種類があります。お墓を建ててしまってから「そんなお墓もあったなんて!」と後悔しないよう、事前にお墓の種類…
2025年2月7日
公営墓地に関するよくある質問
-
公営墓地は安く買えるのですか?
面積当たりの墓所使用料は安いのですが、1区画あたりの面積が広い傾向にあるため一概には言えません。年間管理用は安価です。
-
公営墓地に永代供養墓はありますか?
宗教を選べないので永代供養墓はありませんが、合葬墓や樹木葬などの継承不要のお墓はあります。
