納骨堂にまつわるトラブルは何がある?納骨堂選びの注意点
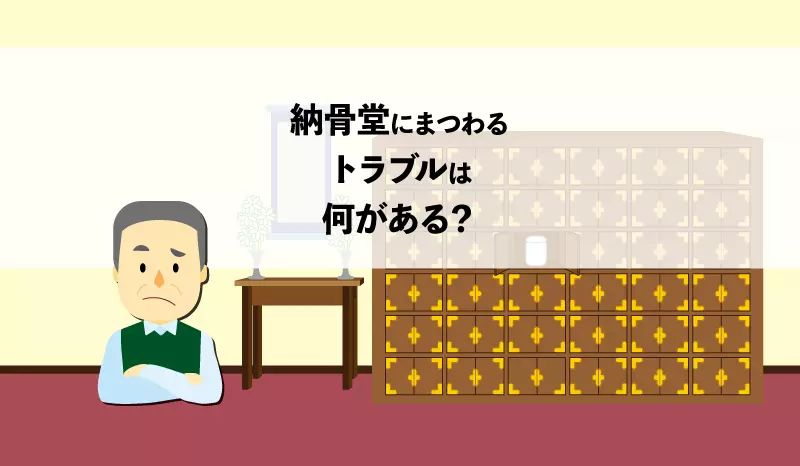
納骨堂を選ぶということはそう何回もありません。今納骨堂を探している方は、もし購入後に良くないことが起こったら……と心配になるかもしれません。
今回の記事では、納骨堂に関するトラブルではどんなことが起きるのか、また、納骨堂選びにはどんなことを気をつけたら良いのかを解説します。
目次
納骨堂とは何か
納骨堂とは、屋内に遺骨を安置する施設です。
近年では、跡継ぎ不要の「永代供養墓」として広く販売されています。
なお、納骨堂自体は新しいものではなく、これまでは遺骨の一時預かり所として利用されていました。
納骨堂は墓石のお墓とどう違う?
納骨堂と墓石のお墓の違いは様々ですが、大きな違いとしては次の二つが上げられます。
- 屋内にあるか屋外にあるか
- 承継が必須か否か
納骨堂は屋内のお墓です。特殊なものを除けばお参りも屋内で行うので、季節や天候を問わず快適にお参りできます。
また、納骨堂には「永代供養」というお寺が将来にわたって故人を供養してくれるシステムが付いている、あるいは付けられることが多く、跡継ぎがいない方でも安心して利用できます。
納骨堂の管理者とのトラブル
数が多いわけではありませんが、納骨堂の利用者と管理者の間に起こったトラブル事例を紹介します。
事例は、国民生活センターなどの資料を参照しています。
- 契約後に想定外の費用がかかった
- お参りがゆっくりできない
- 販売代理店の関係者が不正をした
- 納骨堂が経営破綻した
- 勝手に区画を移動された
契約後に想定外の費用がかかった
「購入後の費用は一切かからない」と説明されていたにもかかわらず、契約後に費用を請求されたケースです。
このケースでは、契約者が契約後に納骨しようとした際、納骨料として一人5万円かかる他に、「納骨法要供養料」や「初檀開眼代」などの名目で22万円がかかると言われ、紛争に発展しています。
参考:国民生活センターADR の実施状況と結果概要について(令和2年度第3回)
この事案は明らかに悪質ですが、年間管理料はかからないけど納骨手数料や納骨法要のお布施が必要、ということはよくあります。
見学のときに、「納骨手数料はかかるのか」、「納骨法要は必須か」、「葬儀や法要は他で営んでもいいのか」など、追加費用や法要の制約などは聞いておくと安心です。
お参りがゆっくりできない
いつでもゆっくりお参りできると説明されていたものの、実際にはお参りに制約が発生するというケースです。
「いつでも逢える」「ゆったり語らえる」と言われて契約したのに、その区画は将来的に全体で100人と契約する予定で、そのためにお参りに待ち時間が発生したり、短時間でお参りしなければならないという制約が発生するということを事前に知らされていなかった、という内容です。
参考:暮らしの判例 国民生活センター 消費者判例情報評価委員会「堂内墓使用契約について準委任契約に基づく中途解除を認めた事例」
特に、参拝室に機械が遺骨を搬送してくる「自動搬送式納骨堂」では、「お参り待ち」が発生することがあります。
参拝室が共用であることに加え、一つの建物に数百~数千など多数の区画を備えることも珍しくないためです。
気になる方は、現状でお盆などの繁忙期はどれくらい混むのか、将来的にどれくらいの区画が埋まる予定なのかなどは確認しておくと良いでしょう。
販売代理店の関係者が不正をした
宗教法人が運営する納骨堂の販売代理店の代表取締役が不正で逮捕されたというケースです。
なお、このケースの参照元は、逮捕を機に契約者が納骨堂を解約して使用料の返還を求めた裁判の判例ですが、逮捕されたことに関しては争点になっていないようです。
参考:暮らしの判例 国民生活センター 消費者判例情報評価委員会「納骨壇使用契約の中途解約の効果と不返還特約」
関係者が不正をしているかを見抜くということは難しいのですが、実際に現地に行ってスタッフや住職と話してみるということは、欠かさずにすることをおすすめします。
納骨堂が経営破綻した
2022年、資金繰りの問題から、札幌市にある納骨堂が突然閉鎖されるという事件が起きました。
なお、これ以前にも、仙台市や福井県で経営破綻した納骨堂がありましたが、これらは別の宗教法人が運営を引き継いでいます。
参考:社説:納骨堂の破綻 自治体は杜撰な経営見逃すな : 読売新聞
参考:破産する寺も続出…「大型納骨堂」がさっぱり売れなくなった理由(吉川 美津子) | マネー現代 | 講談社
もちろん全ての納骨堂が資金繰りに困っているわけではありませんが、ここ何年かで数件起こっている事案です。
施設や設備がメンテナンスされていないような納骨堂は、それにお金が当てられていない可能性があるので、要注意です。
勝手に区画を移動された
実際に当サイト「お墓さがし」に寄せられたご相談では、納骨堂の使用していた区画が勝手に移動されていた、というケースがありました。
契約した区画を無断で移動するということは通常あり得ないのですが、もしこのようなケースに見舞われたら、区画を戻したいのか、解約して使用料を返還してほしいのかなどの要望を考えて、国民生活センターに相談しましょう。
家族や親族とのトラブル
納骨堂は従来の墓石のお墓とは異なるところが多く、親族に相談なく契約を進めてしまうと、揉め事になりかねません。
家族や親族間で起こり得るトラブルとしては、次のようなものが考えられます。
- お墓参りの実感が湧きにくい
- 生前契約したことが親族に伝わっていなかった
- 跡継ぎなのに勝手に墓じまいをしてしまう
お墓参りの実感が湧きにくい
墓参には花、線香、お供え物が必須という価値観は依然としてあります。
しかし納骨堂によってはすべてを実行できません。
墓参に対して制限がある点について、墓参の実感を持ちにくい、という不満を感じる家族や親族がいても不思議ではありません。
生前契約したことが親族に伝わっていなかった
納骨堂は跡継ぎがいない人が多く利用するため、生前契約を受け付けているところがほとんどです。
しかし、せっかく生前契約をしても、残された親族にそれが伝わっていなければ、納骨してくれる人がいません。
生前契約でお墓を購入した場合は、口頭やエンディングノートに記載して親族に契約したお墓がどこなのかを伝わるようにしましょう。
他には、信頼できる知人や、弁護士や司法書士などの法律の専門家と死後事務委任契約を結んでおくのも対策になります。
跡継ぎなのに勝手に墓じまいをしてしまう
現在墓を所有していて、それとは別に納骨堂を契約した場合、今の墓はいずれ墓じまいという形で処分しなければなりません。
しかし墓じまいは過去の先祖の遺骨も処分してしまうことなので、親族の同意がないとなかなか難しいのです。
勝手に墓じまいしてしまうと、親族間で大きなトラブルになります。
納骨堂を選ぶ際の注意点
納骨堂を選ぶときは、以下の点に注意しましょう。
- 必ず現地に見学に行く
- 区画の使用期限を確認する
- 契約後にかかる費用を確認する
- お参りの方法を確認する
- 宗教や法要の制限を確認する
必ず現地に見学に行く
納骨堂を契約する前に、必ず現地に見学に行きましょう。
現地スタッフや住職などと話し、対応が丁寧であるか、信用に足るかは見極める必要があります。
また、ちゃんと清掃や手入れがなされているかも、きちんと管理してもらえるかの指標の一つになります。
区画の使用期限を確認する
納骨堂では、個別区画に使用期限が設けられていることがあります。
期限は納骨堂や区画によって異なり、「契約日から50年」「最後の納骨から13回忌まで」「年間管理料を納める限り」など様々です。
誰が入る予定なのか、いつまで個別でお参りしたいのかなどを考えて、使用期限が問題ないかを確認しましょう。
契約後にかかる費用を確認する
納骨堂において、契約後に発生するかもしれない費用には、以下のようなものがあります。
- 年間管理費
- 納骨手数料
- 納骨法要のお布施
これら全てがかかる場合もありますし、逆に全てかからない場合もあります。
また、檀家として使用する場合は、葬儀や回忌法要を依頼することが必須であったり、戒名授与が必須であったりと、その他のお布施が必要なことがあります。
契約後の費用には何がかかるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
お参りの方法を確認する
納骨堂の種類によっては、思うようなお参りができないことがあります。
例えば、「お供えは個別でなく共用の供物台で行う」「火気厳禁で線香やろうそくを供えられない」「お参りに待ち時間が発生することがある」などです。
現地で確認するのが一番分かりやすいので、現地に行ったときにスタッフに聞いてみましょう。
宗教や法要の制限を確認する
納骨堂を使用できる宗教や、法要はどのようになるかの確認をしておきましょう。
一般に使用者を募集している納骨堂では宗教の制限がゆるい傾向にありますが、「宗教を完全に問わない」「在来仏教であれば宗派を問わない」など、少しずつ要件が違います。
また、「「他所の宗教者は同伴できない」「納骨法要が必須」「回忌法要や葬儀の依頼が必須」など、宗教行事の制約があることもあります。
納骨堂のメリット
トラブルが起こることはあると言っても、やはり納骨堂が増えていることには理由があります。
納骨堂のメリットについて紹介します。
跡継ぎがいなくてもいい
1つは、跡継ぎのいない人や夫婦、家族でも利用できるという点です。
ほとんどの場合で納骨堂には永代供養がついているので、極端に言えば、納骨以降全く縁故者がお参りに来なかったとしても、お墓が荒廃するようなことにはなりません。
家族代々でも利用できる
納骨堂の中でも自動搬送式や仏壇式の場合は、お墓が承継できることが多いです。
跡継ぎはいるけど屋内のお墓が良いので納骨堂を選ぶという人もいます。
家族用の納骨堂であれば、8体前後納骨できます。
ただし、お墓を使い続けるには一般のお墓同様、毎年管理料を払い続ける必要があります。
お墓と比べて費用がかからない
2つめは、一般的なお墓を建てるよりも費用が掛からないという点があります。
日本人の祖先に対する価値観や葬送に対する価値観が変化し、多額の費用を人の死に関してかけなくなってきました。
一般的なお墓を建てる場合は150-300万円が相場とされますが、納骨堂はタイプを選べばこれより断然安く購入できます。
例えば、1人で利用する位牌式であれば安いもので10万円程度、家族で利用できるロッカー式や自動搬送式でも、70-90万円程度で購入できます。
管理の手間がかからない
墓を維持していくことは費用も大変ですが、それ以上に草むしりや墓石清掃などの作業の手間もかかります。
対して、納骨堂の清掃管理などは全て管理者が行うため、お墓の掃除を自分たちでする必要がありません。
また、屋内にあるので、風雨によってお墓が傷むということもありません。
天候に関わらず墓参できる
納骨堂は室内にあるので、天候や気候に左右されず墓参ができ、非常に便利です。
また、自動搬送式などの新しくできた納骨堂ではエレベータやバリアフリー設計が採用されており、快適にお参りできます。
交通アクセスが良い
墓の中には交通アクセスの悪い場所にあるところも多いです。
それは特に高齢化した遺族にとって、墓参の障害になります。
その点ほとんどの納骨堂は、都心で最寄り駅から徒歩圏など交通アクセスのよい場合にあるので、気軽にお墓参りができます。
場所によってはどのような宗派でも納骨が可能
お寺の中にある納骨堂でも、一般のお墓に比べて宗教を問わないところが多いです。
今までは家族の中で1人だけ違う宗派に帰依していると、一緒の墓に埋葬できませんでしたが、納骨堂であればそのようなことはありません。
また、埋蔵される人の範囲を定めていない場合もあり、友達同士などで利用することもできます。
まとめ
墓の維持管理が工数的にも費用的にも負担になるという考えや、葬送関連費用に多額のお金を使いたくないという価値観が広がることによって、従来の墓から納骨堂を選択する人が増えています。
以上で解説したように、納骨堂にはメリットも多々ありますが、しかしトラブルになり得るデメリットもあります。
もし納骨堂への遺骨収納を考えているのであれば、この解説を参考にしっかり検討しましょう。
納骨堂をお探しですか?
お墓さがしでは、全国にある納骨堂を掲載しています。
ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
