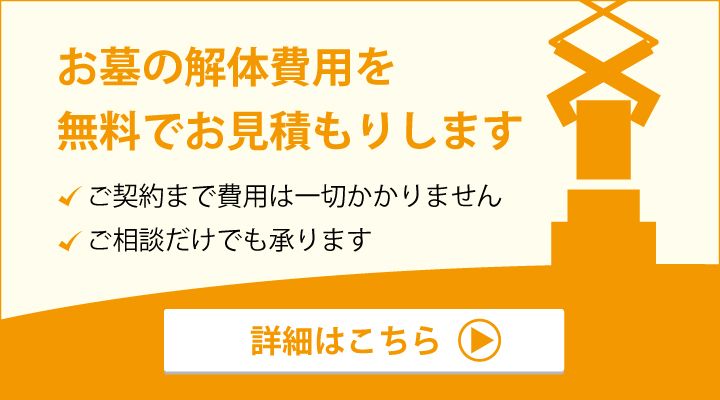墓地を解約したら永代使用料は返還される?売買はできる?

世の中で一般に販売されている商品は、もしも購入して思っていたものと違ったという場合は返品すればかなりの確率で返金してもらえます。
購入ではなくレンタルの場合でも契約更新時に申し出れば、契約は解約できます。
しかしお墓の場合はそのように簡単に契約を解除できないのが現実です。
場合によっては大きなトラブルに発展する可能性もあります。
そこでここではトラブルにならないように墓地の契約を解約するためにはどのような方法と手順があるのか、そして費用がかかる場合にはどの程度なのか、という点について解説します。
目次
墓地の契約を解除する方法と費用
早速ですが、墓地の契約を解約する方法です。
ここから詳しく述べますが、墓地代は一度払ってしまったら全く戻ってきません。
これは墓地を購入して、墓石を建ててしまっているのか、納骨まで済んでいるのかの場合に分けて解説します。
墓石がまだ建っていない場合
墓石が建っていない墓地を返還する場合も、永代使用料は戻ってきません。
墓地を契約するときに支払う費用のことを「永代使用料」と言います。
永代使用料とは、利用者の家が存続する限り(管理料を払い続ける限り)墓地を使用する権利料のことです。
したがって、実際には「墓地」を購入しているのではなく、「墓地を使用する権利」を購入している状態です。
「永代使用料」は、墓地の使用権にかかる費用なので、一度その権利を取得したら、その後に権利を放棄したとしても、返還されません。
永代使用料の返還については、平成19年に実際にあった裁判でも争われています。
内容は、墓地の契約した人が、墓石を建てるまに死亡したため、亡くなった人の子供が墓地に対して永代使用料の一部返還を求めたもです。
しかし判決は、仮に墓石を建てないで永代使用権を解約しても、それはその人の都合で使用権の放棄しただけなので、霊園側に永代使用料返却の義務はない、というものでした。
参考:H19.6.29京都地方裁判所平成19年・第36号墓所使用料前納金返還請求控訴事件
墓石はあるが納骨していない場合
墓石が建っている場合は、墓石を解体して墓所を更地にしてから、返還しなければなりません。
この場合も永代使用料は返還されず、墓石の解体工事も自費で依頼します。
なお、遺骨の移動を伴わないので、行政手続きは必要ありません。
墓石の解体工事費は、8~10万円/㎡が相場です。
ただし、お墓が山の上にあったり、隣接する通路が狭かったりするなど、立地条件によっては相場よりも費用が掛かります。
墓石の解体は、石材店に依頼します。
その墓地で出入りできる石材店が決められている場合は(指定石材店)、そこで見積りを取ります。
出入りできる石材店が無い場合は、自由に石材店を選ぶことができます。
お墓さがしでは、墓石解体くじの無料お見積もりやご相談も承ります。
お気軽にご連絡ください。
納骨している場合
お墓があって納骨している場合は、墓石を解体して墓地を返還することに加えて、行政手続きが必要になります。
この一連の流れは、いわゆる「墓じまい」などと呼ばれます。
この場合も、永代使用料は返還されず、墓石の解体工事費も自費です。
行政手続きでは、「改葬許可申請書」という書類を、その他必要書類と共に、お墓のある自治体に届け出ます。
自治体から「改葬許可書」が交付された時点で遺骨を動かすことができるようになるので、解体工事よりも先に行政手続きを終えるようにします。
承継を放棄して墓地を返すことはできる?
上記は、自分がそのお墓の管理者、つまり祭祀継承者だった場合の、お墓の永代使用権の解約の話でした。
ではそもそも、親などが亡くなってお墓を相続しなければならなくなった場合、相続を放棄することは可能なのでしょうか。
お墓の承継を拒否することはできない
法律上、お墓は「祭祀財産」というものに分類されます。
祭祀財産の承継は一般の相続財産とは全く別のものとして考えられます。
祭祀財産の承継は行政手続きがありません。承継は自動で発生します。
同時に承継を放棄するという行政手続きも存在しないため、相続放棄はできません。
お墓の承継者は誰がなるの?
祭祀財産の承継者は、被相続人(現在のお墓の持ち主)が指定できます。
被相続人の指定がなければ慣習に従い、慣習も分からなければ家庭裁判所が決めます。
また、承継者に指定できる人の範囲などは決まりがないので、法律上は全くの他人でも承継者にすることができます。
ただし、墓地の管理規定上、親族しかお墓を引き継げない場合があるので、注意が必要です。
祭祀財産については、民法第897条では以下のように規定されています。
第897条(祭祀に関する権利の承継)
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
墓地の名義変更をしないとどうなる?
墓地の承継に行政上の手続きはありませんが、契約している墓地で名義変更をする必要はあります。
それでは、お墓のお世話をしたくないからと言って名義変更をしないままにしておくとお墓はどうなるのでしょうか。
墓地は管理料の支払いが止まると、官報や立て札で、使用者に対して墓地の撤去をする旨の通知がされます。
一定期間連絡がなかった場合は墓地の管理者側が墓を撤去し、遺骨は自治体の無縁塚か墓所内の合祀墓に埋葬されます。
勝手に墓地の管理者が撤去しくれるから放っておけば良いと思うかもしれませんが、これは管理者と周囲のお墓に大変迷惑になるので、処分は自分でするようにしてください。
まず第一に、無縁墓の撤去はすぐにはできません。
立て札を建ててから1年間は撤去できないのに加え、立て札を建てるまでも年間管理料が何年か滞っているなどの要件が必要になることもあります。
その間誰もお墓の手入れをしないと、区画内の草木が近隣の区画に侵入するほど茂ってしまい、迷惑を欠けてしまいます。
次に、お墓の撤去費用が墓地管理者側の負担になります。
お墓を撤去してくれればまだいいですが、公営墓地などの場合だと無縁墓が増えすぎて財政的に撤去費用を捻出できない自治体もあります。
放置されればされる程お墓は荒れるので、今度は石が朽ちて隣の区画に倒れたり、最悪の場合は参拝者をケガさせることも考えられます。
お墓を承継したくない場合は、責任を持って自分で処分しましょう。
承継しない場合は墓じまいを
誰もお墓を承継しない場合は、そのままにしておくと祭祀継承者がいないお墓になってしまいます。
自分の先祖や親が無縁仏になってしまうことを避けるには、誰もお墓を承継しないことが決まった段階で、墓じまいを行いましょう。
墓じまいとは、お墓から魂を抜き、墓域を更地に戻してお寺や霊園に返却し、遺骨は永代供養墓などに改葬することです。
墓地の管理者と行政への届出
墓じまいを考えたら、まず墓地を管理しているお寺や管理事務所に届け出て、承諾をもらいます。
遺骨をほかの墓地に改葬する場合は、墓地のある自治体の役所から「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。この手続きに関する費用はかかりません。
新しい墓地の準備
遺骨を新しいお墓に移す場合は、基本的には墓じまいをする前に、新しいお墓を用意する必要があります。
お墓をお寺などの霊園に用意する場合、墓石も含めて費用はだいたい150万~300万円かかります。
新しいお墓を用意しない場合は、かといって遺骨を勝手に処分すると違法になりますから、永代供養墓などへ納骨することになります。
この費用は1番安い、遺骨をほかの人の遺骨と一緒に埋葬する合祀型の永代供養墓で、遺骨1柱あたり5万円です。
もっと安く処分するなら、お寺に遺骨を送ってそのまま合祀墓に入れてもらう「送骨」だと、1柱あたり1万円で供養してもらえます。
閉眼供養をする
遺骨を取り出すときには、閉眼供養を行います。これはお墓から先祖の魂を抜く法要です。
閉眼供養では僧侶に読経をしてもらうことになるので、お布施として1~5万円程度必要です。さらにお寺の霊園ではなく、お寺とは別の場所にある霊園の場合は、そこに僧侶に来てもらう交通費が「お車代」として5000~1万円、また閉眼供養後に行う会食に僧侶が参加しない場合も「お食事代」として5000~1万円必要です。
墓地の更地工事
賃貸住宅の場合、転居する際には、借りた当初の状態に戻す「原状回復」を行うことが借主の義務です。お墓も同様に「借りている」ものなので、お墓を返す際には、原状回復を行う必要があります。
つまり墓域から墓石を撤去し、納骨室を解体し、墓域を更地に戻すことです。
この作業は石材店に依頼することになりますが、費用としては1平方メートルあたり10万円程度が相場です。
新しい墓地、納骨堂への遺骨の納骨と開眼供養
遺骨を新しいお墓に埋葬する場合は、受け入れ先の「受入証明」「埋葬証明」などが必要なので、事前に請求しておきます。
そして遺骨を新しいお墓などに納骨する時にも、お墓に先祖の魂を呼び戻す、開眼供養を行う必要があります。新しいお墓がお寺にある場合はそのお寺の僧侶、公営、民営の霊園の場合はどこかの寺院に頼んでその寺院の僧侶に読経してもらいます。その際にもお布施が1万~5万円必要です。
さらに、場合によっては閉眼供養か開眼供養のどちらかのときに、参列者の会食を用意することが一般的です。相場としては1人あたり5000円程度の予算です。
このように「墓じまい」をする場合には、新しいお墓の取得費用を除いても、50~100万円程度のお金がかかります。
墓地を売買することはできる?
先ほど書いたように、「墓地を購入する」と言ってもそれは所有権の取得ではなく、使用権の取得なので、墓地自体は自分の所有物にはなりません。
したがって、墓地をほかの人と売買することはできません。
では「使用権」の売買はどうなのかというと、法的には不可能ではありませんが、お寺や霊園と墓地の取得時に交わす契約書のほぼすべてで、「無断で墓地の転売や譲渡した場合、使用権を取り消す」という規定が設けられています。したがって、この使用権の売買も不可能だと言えます。
まとめ
墓地はいったん契約してしまうと、まだ墓石さえ立てていない時に契約を解約しても、取得に要した永代使用料は返還されません。ましてや墓石を建て、納骨までしてしまうと、墓域を更地にするために数十万円の費用が追加でかかってしまいます。
ですから墓地を購入する際には、後で失敗したと思わないように、あるいは家族や親族などからクレームが来ないように、よく検討し、必要な人とは十分に話し合って決定しましょう。
墓じまいの見積もりサービスに相談してみよう
お墓さがしでは、墓じまいをパック料金で承っています。
お見積り・ご相談を完全無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。