埋葬許可証の再発行はできる?紛失した時の対処法
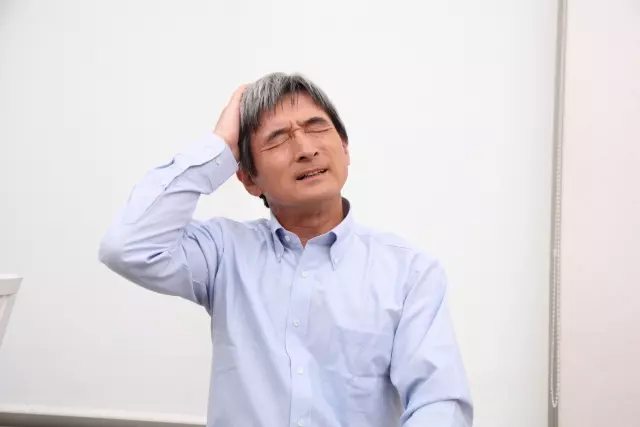
ご遺骨を墓に納骨するには、埋葬許可証が必要です。
ですが、しばらく自宅で安置していた遺骨をいざ納骨しようとしたら、埋葬許可証がどこに保管したか分からなくなってしまうということは珍しくありません。
今回の記事では、埋葬許可証の再発行について解説します。
目次
埋葬許可証とは
埋葬許可証は、納骨の際に墓地の管理者に提出する書類です。
埋葬許可証は、葬儀が終わり、火葬場で荼毘に付した後、火葬許可証に火葬日時などの事項を明記、証印し、遺族に渡されます。
火葬許可証は、市町村役場に死亡届を提出し、受理される時に交付されます。
現在は1枚の書類で兼ねているので、あわせて「死体埋火葬許可証」と表記することもあります。
発行した自治体により、表記や呼び方は変わります。
埋葬許可証はいつ、どこでもらうの?
死亡診断書(または死体検案書)と死亡届を市町村役場に提出して受理されると、火葬許可証が発行されます。
火葬許可証がなければ、火葬はできません。葬儀の前に必ず、死亡届の提出手続きをします。火葬許可証は、火葬を行う時に提出します。
火葬が終わると、火葬場が、火葬許可証に日時などを記入、証印し、遺族に返却します。
証印が押されて返却された書類が「火葬証明書」および「埋葬許可証」になります。
埋葬許可証と火葬許可証との違いは?
「死体埋火葬許可証」と呼ばれ、まとめて扱う埋葬許可証と火葬許可証は、厳密には、まったく別物です。
火葬許可証は、火葬を行うことの許可証です。
火葬許可証は死亡届が受理されたところで発行されます。
法律上は、埋葬は土葬のことです。本来、埋葬許可証は、土葬の許可証になります。
遺体やお墓に関しては、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)という法律で規定されています。
第2条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
(略)
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(略)
第8条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
法律上は、土葬は禁止ではありませんが、現在、条例で土葬を禁止している自治体が多く、ほとんどのところで火葬になります。
本来の意味で「埋葬許可証」は、発行していません。
死亡届を提出後、火葬許可証により、火葬が行われます。
火葬場で荼毘に付し、火葬場が火葬許可証に証明の印を押し、遺族に返却します。
証印のある許可証が納骨の許可となるので、便宜的に「埋葬許可証」と呼びます。
埋葬許可証は大切に保管する
納骨は、いつまでにしなければいけないとは決められていません。
仏教では、四十九日は忌明けとし、一般的に、四十九日の法要とあわせて納骨を行います。
四十九日に墓が間に合わない時は、一周忌や三回忌の法要にあわせるケースもあります。
昨今、自分らしい最期を迎えるために「終活」をする方が増えています。
終活は、身の回りの生前整理や遺言の準備、ご自身のご希望の葬儀や墓を用意する活動です。
四十九日の時期にこだわらず、自由に納骨式を行う人も増えています。
火葬を行った後、納骨までには日数があきます。その間、大切に埋葬許可証を保管してください。
万が一、埋葬許可証を紛失したら、再発行の手続きが必要となります。
再発行は有料ですし、手続きに時間がかかるケースもあります。しっかり場所を決めておきましょう。
骨壺といっしょに、埋葬許可証を骨箱(桐箱)に入れておくと安心です。
埋葬許可証は何に必要なの?
埋葬許可証は、埋葬の時以外でも、墓を移動させる時や分骨にも必要になります。
納骨のとき
火葬の後、納骨する際に埋葬許可証となります。
納骨する寺院や霊園・霊苑など、墓地の管理者に埋葬許可証を提出する義務があります。
分骨するとき
分骨は、故人の遺骨を複数に分けて供養することをいいます。
納骨する時は、かならず埋葬許可証が必要ですが、1枚しか発行しません。
分骨される方は、火葬前に「分骨する旨」、「必要枚数」を係の人に伝えます。
必要な枚数分の分骨証明書を発行してもらえます。
納骨の際に、2か所目以降は分骨証明書を渡します。
後から分骨が決まったら、先に納骨した墓地や霊園の管理者に分骨証明書を発行してもらいます。
散骨するとき
散骨については、法律上、埋葬許可証提出の規定はありません。
ただし、業者に散骨を依頼する場合は、業者に埋葬許可証の提出を求められる場合があります。
遺族の方ご自身がすべての遺骨を散骨する場合は、埋葬許可証は不要です。
なお、一部、散骨して、残りは納骨のケースは、埋葬許可証が必要です。
また、ご自宅にて供養する「手元供養」のケースは、埋葬許可証は不要です。
ですが、将来的に、納骨する可能性はあるので、処分せずに、残すことをおすすめします。
お墓を移動させるときは?
お墓を移動させることを、改葬と言います。
今お墓から遺骨を取り出し、新しいお墓に納骨する際も埋葬許可証は必要なのでしょうか。
改葬の際に必要な書類は、埋葬許可証ではなく「埋葬(埋蔵)証明書」です。
埋葬証明書は、現在のお墓の管理者から発行してもらいます。
市役所に埋葬証明書と合わせて改葬許可申請書を提出すると、「改葬許可証」が発行されます。
新たなお墓に納骨する場合は改葬許可証を提出しましょう。
埋葬許可証の保管期間
墓地や納骨堂の管理者は、納骨時に受け取った埋葬許可証を5年間保管することが義務付けられています。
また、公文書の分類基準により、自治体の火葬許可証の保存年数は5年間とされています。
死亡届を出した自治体に5年間の保管義務
自治体の公文書を適切に保存するための分類基準により、火葬許可証は5年間、保存することを定めています。
死亡届を受理し、火葬許可証を発行した市町村役場で5年間、保管します。
墓地や納骨堂の管理者に5年間の保管義務
墓地や納骨堂の管理者は、納骨時に受け取った埋葬許可証を5年間、保管するように墓埋法で決められています。
第16条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。
埋葬許可証を再発行するにはどうすればいいの?
埋葬許可証は納骨の際に必ず必要になります。
長年自宅安置していた遺骨をいざ納骨しようとしたときに、埋葬許可証がどこにあるか分からなくなってしまうことも珍しくありません。
埋葬許可証の再発行はどこでできるのでしょうか。
再発行は役所でできる
万が一、紛失してしまった場合でも、亡くなってから5年未満は、死亡届を受理した市町村役場で再発行できます。
再発行には、手数料がかかります。
金額は自治体により変わりますので、対象の市町村役場に、お問い合わせください。
誰が申請できるの?
再発行を申請できるのは、限られた人だけです。死亡届の届出人や故人の直系親族、祭祀継承者だけが申請できます。
直系親族は、親子や祖父母と孫みたいに、世代が上下に直線的に連なっている親族のことをいいます。
祭祀継承者は、墓の管理や法要を主催する人になります。祭祀継承は、民法897条にて規定しています。
(祭祀に関する権利の承継)
第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
祭祀継承者は、一般に家族の中で特定の一人がなります。誰が、祭祀継承者になるかは、特に決まっていません。故人の生前の希望や遺言があれば、それを優先します。家族内で紛争があった場合は、家庭裁判所で決めるケースもあります。
申請書の提出
死亡届を受理した市町村役場指定の申請書を記入して、再発行を申請します。
死亡届の届出人以外の人が申請する場合、戸籍や住民票のように申請者と故人の続柄を示すものを用意します。
本人確認書類の用意
申請する時に、免許証など本人を確認する身分証明書が必要です。死亡届を受理した市町村役場が遠方の場合や申請者が窓口に行けない場合には郵送でも申請できます。
郵送の場合は、身分証明書のコピーを同封します。
詳しくは、対象の市町村役場にお問い合わせください。
5年以上経った埋葬許可証の再発行
死後5年以上経っている場合は、火葬証明書も必要となってきます。
「火葬証明書」の取得
火葬証明書とは、遺体の火葬を行ったことを証明する証書のことです。納骨をする際に、火葬許可証にかわるものとして用いられます。
火葬証明書は、火葬を行った火葬場に申請します。
公営の火葬場での火葬簿の保存年限は、自治体によって異なります。
例えば、大阪市や川崎市は30年としていますが、大分県佐伯市では5年としています。
自治体の定める火葬簿の保存期限内であれば、火葬証明書を再発行できます。また、民間の火葬場でも保管されている可能性があります。
いずれにしても、まずは対象の火葬場に問い合わせてみましょう。
埋葬許可証の再発行には市役所に連絡
埋葬許可証の再発行は、死亡届を受理した市町村役場が行います。
自治体により、申請書類や費用、手続きなどは異なります。まずは、対象の市町村役場にご確認ください。
まとめ
埋葬許可証は納骨の際に必要になります。
万が一紛失しまった場合は、死亡届を受理した市区町村の役所に再発行をお願いしましょう。
また、もし死後5年以上たっている場合は、埋葬許可証の再発行に火葬証明書が必要になってきます。
火葬証明書の再発行については、火葬を行った火葬場に問い合わせてください。
手数料や申請書類は自治体によって異なりますので、対象の役所に確認しましょう。
墓地・霊園をお探しですか?
お墓さがしでは、全国にある樹木葬、納骨堂、永代供養墓、墓石のお墓を建てられる霊園などを掲載しています。
ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
