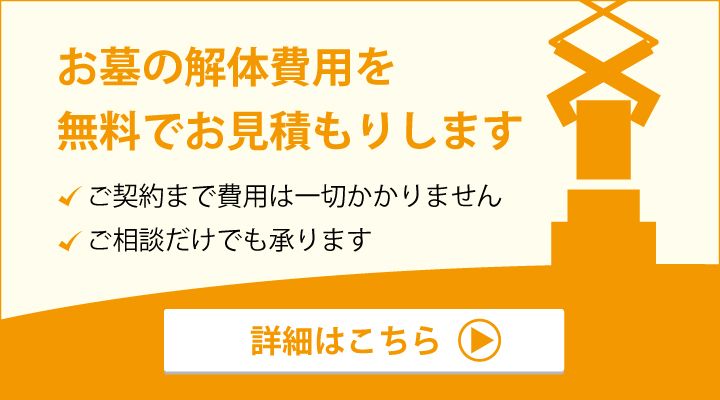檀家を揉めずにやめるには?離檀の手順とトラブルの対処法

お寺にお墓を持っている家はどこでもそのお寺の檀家になっています。
しかし檀家になっていることのメリットが感じられなくなってきたり、管理料を払うのが無駄なような気になってきて、近年では檀家をやめることを考える人も増えています。
しかし檀家をやめる時には、やめさせたくないお寺側ともめた結果、高額な離檀料というお布施を請求されてトラブルが発生していることも多いのです。
そこでここでは、もめずに檀家をやめるにはどのようにしたらよいのか、という点について解説します。
目次
檀家とは何か
壇家とは、お寺に仏事全般の面倒を見てもらう代わりに、お寺を経済的に支える家のことです。
浄土真宗の場合は、檀家ではなく「門徒」と言います。
檀家の役割
お寺の檀家になるとどういうことができるかというと、まず、家族が亡くなった時や、お盆、お彼岸など葬儀や法要の時に家や葬儀会場に僧侶が来て読経してくれます。
また亡くなった家族に戒名をつけてくれます。
このように自分の家が、仏教上の何らかの法要をする場合、お寺が窓口兼担当者になってくれます。
さらに、そのお寺にお墓を持つことで、お墓の管理や、遺骨を埋葬する手続きなどもしてくれます。
墓地を経営するには、「墓地、埋葬等に関する法律という法律」(墓埋法)に則って、市区町村の許可が必要です。
厚生労働省の「墓地経営・管理の指針等について」によると、「墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。」とされています。
寺院は宗教法人にあたるため、一定の条件を満たすと墓地の経営許可を取ることができます。
参考:墓地経営・管理の指針等について
そのため、現在でも墓地の供給の多くは寺院に頼っているのが実情です。
檀家になると、法要の都度そのお寺にお布施を払い、お葬式の時には高額な戒名料を払い、さらに毎年お墓の管理費を払います。
その意味で檀家はお寺の収入源であり、「顧客」なのです。
檀家の起源
この「仏教徒は誰でもどこからのお寺に所属」する、という制度が始まったのは江戸時代からです。
江戸時代は、キリシタンが禁制されていたことでもわかる通り、ほぼ100%の日本人が仏教徒でした。
江戸幕府は全国民が仏教徒であることを利用して、お寺による人民統制として、日本人は必ずどこかのお寺に所属しなければならないということを決めたのです。これを寺請制度(てらうけせいど)と言います。
現代では100%の日本人が仏教徒ということはありませんが、この寺請制度の名残で、多くの家がお寺に所属し、檀家になっています。
檀家や門徒をやめる家…「檀家離れ」の背景
江戸時代の寺請制度から始まった檀家というものを、近年やめる人、あるいはやめたいと思う人が増えています。
お墓が遠くなった
1つは江戸時代から昭和時代の前半くらいまでは、人は自分の生まれた故郷を離れることが少ない状況でした。
先祖代々からの家を継ぎ、昔から住んでいる地域に住み続けるという人が圧倒的に多かったのです。
自分の所属しているお寺を菩提寺と言いますが、この菩提寺も自宅から近隣にあることが大半だったので、お墓参りなどにも必要の都度気軽に行くことができたのです。
しかし現代では、地方に生まれてもその地方に住み続けるという人は極端に減ってきました。
地方出身者は東京、大阪といった都心に就学や就職のために転居し、そのまま住み続けることが増えてきたのです。
東京、大阪などだけが人口増加し、地方がどんどん過疎化しているのはこういった事情があります。
こうなると、菩提寺は自分の住んでいるところから遠隔になってしまうため、お墓参りをすることはなかなか難しくなります。
すると檀家であり続けることが困難になるので、檀家を離れて自分の住んでいる近隣の霊園などにお墓を移そうという考えになるわけです。
これが檀家をやめる人が増えている1つの理由です。
管理費や寄付を支払いたくない
もう1つは、日本人の宗教観が変化したことです。
かつては、亡くなったら僧侶を呼んで仏教式のお葬式を挙げ、定期的にお墓参りをして法要を行うことが当たり前でしたが、近年は仏教という宗教を信じる人が減り、無宗教でのお葬式を行うことも増えてきました。
そうなると檀家になっている意味がなくなるので、檀家をやめることを考えるようになるのです。
さらに、菩提寺に払う毎年の管理費の意味も感じられなくなり無駄な支出に思えるので、その支払いをやめるためにも檀家を離れることを考えるのです。
檀家から抜けるメリット・デメリット
では檀家をやめることにはどのようなメリットがあるのでしょうか。またデメリットはないのでしょうか。
壇家をやめるメリット
檀家をやめるメリットは何といって経済的な支出が減ることです。
先ほど書いたように檀家であることは、管理費などを定期的にお寺に納めることなので、檀家をやめればその支出がなくなります。
管理費のほかにも、菩提寺が改修したり、新しい施設を作るときには寄付を求められます。
寄付は義務ではありませんが、払わないと自分のお墓に不都合が起こりそうな気がして、つい払ってしまいます。
檀家を離れればそのような支出もなくなります。
壇家をやめるデメリット
檀家をやめる最大のデメリットは、お寺に自分の家のお墓を持ったままだと、そのお墓は無縁墓として撤去されてしまうことでしょう。
お墓に埋葬されている先祖代々の遺骨も、無縁仏として他人の遺骨と一緒に処分されてしまいます。
ほかにも、何か仏教上の法要や仏教式のお葬式などをする場合に、頼りにするところがなくなるというデメリットもあります。
ただ、お寺は檀家ではなくても頼まれればお葬式で読経も行いますし、戒名もつけます。
ですから、檀家になっていなければ絶対に仏教式のお葬式を行えないということはありません。
もめずにお寺との付き合いをやめたいときの手順
檀家を離れるメリットとデメリットを比較した上で、それでも檀家をやめる場合は以下の手順で行いましょう。
まずは菩提寺の住職に相談する
事前の相談は離檀において最も重要なステップと考えてください。
まずは離檀を決定事項としてではなく、相談としてお寺に話します。
間違っても、最初から「離檀」という言葉は出してはいけません。
下記の事項を丁寧に伝えましょう。
・日頃お墓のお世話をしてもらっている感謝
・あまり顔を出せていないことの謝罪
・やむを得ず墓じまいにすることになった理由
檀家やめられてしまうことは、お寺側にとっては、貴重な収入源である顧客を1軒失うことです。
ですからお寺は基本的に檀家を離れることを歓迎しません。
にもかかわらず、お寺側の了解を得ずに勝手に檀家を離れようとするともめる可能性があります。
高額なお布施、つまり離檀料を請求されてしまうこともあり得るでしょう。
まずは事情を丁寧に説明して、お寺の承諾を得ることが必要です。
離檀の手紙の書き方
本来はお寺に直接おもむいて挨拶するのがベストですが、住まいから遠く訪問して相談することが難しい場合は、手紙で離檀の相談をしましょう。
ただしあくまでスタンスは、「離檀の通知」ではなく「墓じまいの相談」であることに注意してください。
書く内容は、どうしてもお墓参りができず先祖に申し訳ないので離檀するしかない、という理由と、今までのお世話に感謝する、というものにすることが大切です。
墓じまいの業者を選ぶ
離檀の目処がついたら、墓じまいの準備をします。
墓じまいとは、遺骨を取り出し、お墓を撤去し、墓地を更地にして返還することです。
まずは墓じまいを頼む業者を手配しましょう。
ここで注意が必要なのは、墓地に立ち入れる業者が指定されている場合です。
指定業者がいると解体費用も言い値になってしまうので、費用は高くなる傾向にあります。
立地などにもよりますが、解体費用の相場は1㎡あたり10万円前後です。
指定業者に頼むとしても必ず事前に見積もりを取りましょう。あまりに費用が高額であればそのまま受け入れてはいけません。
他の業者などに相談して、見積もりが妥当なのかを調べてみましょう。
また、自由に業者を選べる場合も注意が必要です。
悪質業者だと、お墓の基礎や納骨室を解体しないでそのまま埋めてしまうことがあります。
これは見た目には分からないので、次に墓地を利用する人が墓石を建てる段階になって、明らかになります。
そうなるとお寺や次の利用者に迷惑をかけてしまうことになるので、あまりに費用が安い業者などは要注意です。
墓じまいをする
業者が決まったら墓がある自治体の役所に届け出て、「改葬許可証」を発行してもらいます。
改葬許可証が出ると遺骨を墓地から移動することができます。
なお、遺骨を取り出すときには「閉眼供養」という法要が必要になります。
お寺と打ち合わせて、解体の前に供養してもらいましょう。
後は業者に遺骨を取り出してもらい、解体工事をして墓地を返還すれば墓じまいは終わりです。
離檀料を払う
檀家をやめる時には、今までの菩提寺への感謝をお金で表すこととして、離檀料を支払います。
離檀料の支払いは法的な義務ではないので、絶対に払わなければならないということではありません。
しかしお墓を処分して新しい墓地に遺骨を埋葬するためには、墓地管理者(お寺)の許可がいるため、離檀料は支払ったほうが無難です。
悪質なお寺だと数百万円単位の高額な離檀料を請求されて訴訟になることもありますが、一般的な離檀料の相場は十万円程度です。
離檀にまつわるトラブル
離檀にまつわるトラブル
- 離檀させてくれない
- 離檀料があまりに高額
檀家とは法的な制度ではありません。
法的な制度でないことは一見自由でよさそうですが、しかし別の意味で言えば「決まりがない」ということです。
決まりがあれば、お互いに心の中はどうであろうと、法律に従って粛々と手続きを行うだけのことで、トラブル発生の余地はありません。
しかし、決まりがないと、離檀されるお寺との関係性が悪ければ悪いほど、あるいはお寺がお金に執着すればするほど、トラブルが発生しやすくなります。
離檀させてくれない
まず、そもそもお寺に離檀を認めてもらえない場合があります。
墓じまいをする際に離檀を認めてもらえないと、次のような弊害が起こります。
改葬許可証を発行してもらえない
墓地から遺骨を移す際は、お墓のある自治体の役所から「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。
そのためには、書類の提出と併せて墓地管理者の署名・捺印または、墓地管理者が発行する「埋蔵(埋葬)許可証」がないと許可が出ません。
墓地管理者とは、つまりお寺のことです。
お寺が離檀を認めない場合は当然署名も書類の発行もしてもらえないので、遺骨が取り出せないという事態になります。
解体業者が立ち入れない
改葬許可は役所に相談することで発行してもらえることもありますが、今度は業者が墓所内に立ち入れないという問題が起こります。
当然檀家墓地はお寺の敷地内にあるため、お寺が業者を立ち入らせないということも考えられます。
離檀を止める権利は寺院にはない
ちなみに、法律上離檀を止める権利は寺院にありません。
同じ民事でも借金のように借用証があれば支払わなければなりませんが、檀家になる際にそのような契約書は作成しませんから、正確に言うと債務さえ存在しなのです。
ましてや、現代の日本は憲法によって宗教の自由が認められています。
宗教の自由があるということは、どのお寺の檀家になろうと、あるいは檀家をやめようと、その人の意思で行動してよいということです。
ですから高額な離檀料などを請求して、檀家をやめることを妨げるようなことがあれば、それは違法行為なのです。
離檀料があまりに高額
離檀は認められても、その代わりに数百万円もの離檀料を要求してくるお寺がごくたまにあります。
ちなみに、離檀料の相場は法要1回分程度なので、相場は3-15万円程度でしょう。
もちろんすべてのお寺に当てはまることではありませんが、離檀する上では注意しましょう。
離檀料を支払う義務はある?
離檀料についてはやはり法律上の規定がなく、実際に支払いの義務はないとする考え方が多勢のようです。
実際、過去にも数百万円の離檀料を請求された人がお寺を訴えた裁判がありましたが、判決は離檀料を支払う義務がないという内容でした。
ですから離檀料でトラブルになった場合は、弁護士などに相談すれば、弁護士がお寺との間に入って交渉し、離檀料を正当なレベルに直してくれるでしょう。
離檀でトラブルになった時の対処法
それでは、実際にトラブルになってしまったらどうすればいいのでしょうか。
まずは冷静に話し合い
まずは、双方納得する努力をしましょう。
離檀料は義務ではなくあくまでお気持ちであること、お墓を無縁にしてしまうとお寺に迷惑をかけてしまうことなどを穏便に根気よく伝えます。
相手が感情的になっていても、こちらが乗っかってしまうと収集がつかなくなってしまします。
あくまでも冷静に話し合いをしてもらうことが重要です。
本山に相談する
どうしても当事者間で解決できない場合は、そのお寺の「本山」に連絡しましょう。
本山とは、お寺の本社のようなものです。本山はどのお寺にも必ずあります。
役所の窓口に相談する
改葬許可に必要な書類をお寺に用意してもらえない場合でも、役所に相談すれば改葬許可を出してもらえます。
改葬許可が出れば遺骨を墓地から出すことができます。
納骨室が地上にある丘カロートのものなど、構造が単純であれば自分で遺骨を取り出せるでしょう。
本来は遺骨を取り出す前に閉眼法要という法要をするのですが、とりあえず人質たる遺骨は確保することができます。
ただし、業者でないと遺骨を取り出すことが難しい場合は、やはり業者が墓所内に立ち入らなければなりません。
弁護士は最終手段
本当にどうにもならない場合はいよいよ弁護士に相談します。
弁護士に相談するとなると費用も掛かるので、本来はここまで来る前に解決するのが望ましいです。
ただし実際に訴訟に発展することは珍しいです。
判例もあるので、訴訟をちらつかせた時点でお寺も引き下がるでしょう。
まとめ
檀家を続けることも、やめることも、決める権限は檀家側にあって、お寺側にはありません。
どのスーパーで野菜を買おうと消費者の勝手、ということと全く同じです。
とはいえ、お寺にも感情があり、なおかつ墓地管理者という立場から墓じまいの妨害をすることもできます。
したがって、お寺を離れたいと考えたときには、できるだけトラブルにならないように、穏便に進めるほうが得策です。
そのためには、以上で解説したことを参考に離檀を実行しましょう。
墓じまいの見積もりサービスに相談してみよう
お墓さがしでは、墓じまいをパック料金で承っています。
お見積り・ご相談を完全無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。