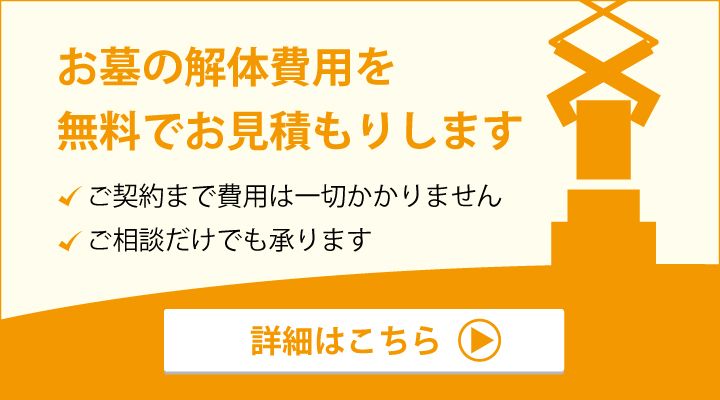墓じまい後の遺骨の改葬や処分の方法についてわかりやすく解説します!

近年では葬送の多様化や、少子化・核家族化などの影響で、墓じまいを考える人が増加しています。
終活の一環として墓じまいを行う場合もあり、墓じまいについて知っておくことで、子や孫など次の世代の負担を減らすことができます。
この記事では、墓じまいと、その後の遺骨の改葬方法について解説します。
目次
墓じまいをした後の遺骨はどうする?
墓じまいをした後の遺骨の供養の方法には、主に以下のようなものがあります。
墓じまいをした後の遺骨の供養先の例
- 永代供養付きのお墓に納骨する
- 散骨する
- 自宅供養をする
永代供養付きのお墓に納骨する
永代供養とは、親族に代わり、霊園や墓地の管理者がお墓や故人を供養してくれることを言います。
永代供養がついているお墓を「永代供養墓」と言いますが、承継者がいなくても使用できることから、子どもがいない方や、ご家族にお墓の負担を残したくない方などに人気です。
永代供養墓には、以下のようなものがあります。
樹木葬

樹木や花壇は、石に比べて安価なため、費用を抑えることができます。
樹木葬には、大きく分けて「里山型」と「都市型」2つの種類があります。
里山型

墓標として新たに植えた樹木の下に直接納骨することが多く、遺骨は時間をかけて土に還ります。
自然志向の方には一番合っている埋葬方法ですが、山の中にあるためアクセスが悪く、車でしか行けない場所にあることもあります。
里山型の樹木葬の費用相場は、5~60万円程です。年間管理費はかからない傾向にあります。
都市型

シンボルツリーの下に遺骨を埋めるというタイプよりは、花壇に納骨スペースを設けるタイプのものが多くあります。
里山型に比べると、自然の中で眠るというイメージから離れてしまいますが、アクセスが良く、お参りしやすい立地にあることが特徴です。
納骨スペースに遺骨を納めるときは、骨袋や骨壺に入れた状態で埋葬するものが多く、その場合は遺骨が土に還らないこともあります。
都市型の樹木葬の費用相場は、5万~100万円です。
納骨堂

霊廟(れいびょう)とも呼ばれます。
納骨堂には、大きく分けて「ロッカー式」「自動搬送式(マンション型)」「仏壇式」などがあります。
ロッカー式

夫婦から家族で使用でき、収容人数は1~4名程度のところが多く、大人数の使用には向きません。
ロッカー式納骨堂の費用相場は、50~100万円です。
自動搬送式(マンション型)

建物の外観がマンションのようなものであることが多いことから、マンション型納骨堂とも呼ばれます。
遺骨は普段、バックヤードに保管されており、受付か墓前のリーダーにカードをかざすと、遺骨を収蔵した厨子が運ばれてきます。
都市部に多く、交通アクセスが良いことが特徴です。
自動搬送式(マンション型)納骨堂の費用相場は、80~120万円です。
仏壇式
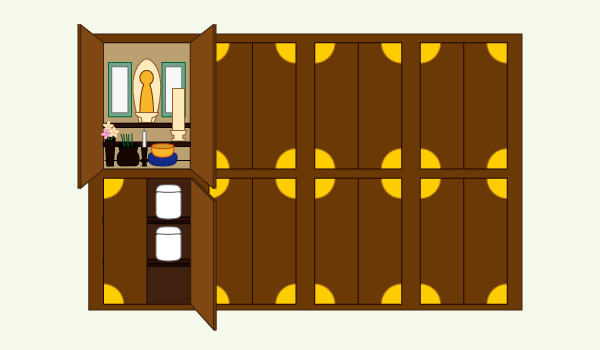
上段が仏壇、下段が遺骨安置スペースになっています。
遺骨安置スペースが大きいものが多く、10名以上収蔵できるところもあります。
納骨堂は、基本的に宗教不問のところが多いですが、仏壇式納骨堂は、宗派を指定するところがやや多い傾向にあります。
仏壇式納骨堂の費用相場は、100~200万円です。
永代供養付き一般墓

一定期間が経過したり、承継者がいなくなったときに、霊園内にある永代供養墓に遺骨が移されます。
また、墓地・霊園によっては、永代供養墓に移動せず、墓石を解体しないまま永代にわたり供養してもらえるところもあります。
永代供養付き一般墓の費用相場は、100~360万円程度です。
費用に関しては、一般のお墓と変わりません。
合祀墓

合葬墓や永代供養塔などと呼ばれることもあります。
骨壺から焼骨を出した状態で納骨するものが多く、その場合遺骨が他の人のものと混ざります。
そのため、一度埋葬すると取り出すことができない点に注意しましょう。
合祀墓の費用相場は、3~30万円程度です。
その他の永代供養墓
オブジェの中に埋葬するタイプ、屋外に設置された棚のようなものに納骨するタイプなど、他にも様々な種類の永代供養墓があります。
改葬以外の遺骨の供養方法
改葬以外の遺骨の供養方法には、散骨と手元供養があります。
散骨する

海洋散骨、山林散骨、バルーン葬など、形態は多様です。代表的な海洋散骨の費用は、全て業者に委託する場合は5万円~、家族が船を貸し切って散骨する場合は15~30万円程度が相場です。
自宅供養をする

長年お墓に納骨していた骨壺は中に水が溜まっていることがあるので、一度お骨を乾燥することをおすすめします。乾燥の費用は、5千~1.2万円程度です。
遺骨を処分したい場合の方法
墓じまいをした際に自分の知らない古い遺骨がでてきた、遠縁の身寄りのない親せきの遺骨のため思い入れがないなど、遺骨がいらないケースがあります。
いらないからといってゴミにだしてしまうと、死体損壊・遺棄罪に問われます。
刑法190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する
遺骨を処分したいときは、2つの方法があります。
業者に依頼して散骨してもらう
業者に遺骨を送り、海や山に散骨してもらうという方法があります。
業者に散骨を依頼する場合は、1体あたり5万円前後の費用で済むため、おすすめです。
「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)という法律によって、市区町村の許可した墓地以外には遺骨を埋葬できない決まりになっています。
しかし、遺骨をパウダー状にして撒く散骨に関しては、法律での規定がないため、黙認されています。
散骨を自分でやるのは、散骨できる場所限られていたり、粉骨の作業があるので、業者に任せるのが無難です。
合祀墓に納骨する
合祀墓に改葬するという方法があります。
合祀墓は、安いものでは一体あたり3万円で納骨することができます。
合祀墓では、管理費がかからないところがほとんどなので、納骨後の負担はありません。
遺骨を運ぶ方法3つ

運ぶ方法としては、以下の3つが挙げられます。
1.自動車・公共交通機関
墓じまいをするお墓の周辺の地域にお住まいの場合は、自動車・公共交通機関で遺骨を運ぶことが多くあります。
遺骨を持って公共交通機関に乗ることは、法律上は問題ありませんが、他の乗客に不快感を与えないように配慮する必要があります。
風呂敷などの布で骨壺を包んだり、バッグに入れて運びましょう。
2.ゆうパックによる送骨
日本郵便のゆうパックのみ、遺骨を郵送することが可能です。
ヤマト運輸や佐川急便などの他の運送会社は、遺骨を送れないので注意しましょう。
ゆうパックで遺骨を送るときは、骨壺に水が入っていないか確認します。
水がたまったまま郵送すると、水が漏れてしまう危険性があるためです。
カロート内は湿気が多いため、結露によりカロート内に水がたまることがあります。
水がたまっていたときは、風通しの良い場所で遺骨を乾燥させましょう。
また、輸送中に段ボール内の遺骨が骨壺からこぼれないように、骨壺の蓋をガムテープなどで固定しましょう。
骨壺が破損しないように、段ボール内に緩衝材をつめて準備を整えてから、郵便局やコンビニエンスストアなどの取扱所へ持っていきます。
墓じまいするお墓が遠方にあってとりにいけない場合は、墓じまいの工事をする石材店が遺骨を送ってくれることがあります。
遺骨を送ってほしい場合は、契約前に石材店に相談しましょう。
3.NPO法人の納骨サービスを利用する
送骨のフォローから永代供養塔への納骨までサポートしてくれるNPO法人のサービスがあります。
NPO法人 終の棲家なき遺骨を救う会では、ゆうパックで送骨するのに必要な段ボールや緩衝材、書類などを一式送り、指示通り遺骨をゆうパックで送ると、東京都新宿区南春寺の合祀墓に納骨してもらえます。
送骨のサポートから納骨までの費用総額は、3~5万円です。
まとめ
墓じまいとは、墓石などを片付け更地にし、土地を寺院や霊園の所有者に変換することです。
墓じまいを行う場合は、埋葬されている遺骨も同時に移動させる必要があります。
墓じまいを行う時期に決まりはありません。ただし、墓じまいには、時間と費用がかかるため、早めの準備が必要です。
墓じまいの手順は大まかに親族や寺院への確認、書類の発行などの手続き、遺骨の改葬か他の供養を行うの順にします。
墓じまい後の遺骨の改葬は、新しくお墓を用意したところに埋葬します。
新しくお墓を持たない場合は、散骨や手元供養にします。
土葬のお墓を改葬する際、遺骨が残っていなければ行政手続きは不要ですが、遺骨の有無は掘り返すまで分からないので、手続きはしておくことをお勧めします。
墓じまいの見積もりサービスに相談してみよう
お墓さがしでは、墓じまいをパック料金で承っています。
お見積り・ご相談を完全無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
墓じまい後の遺骨の改葬や処分の方法についてわかりやすく解説します!に関する記事
-
墓じまいとは?費用と流れを詳しく解説!トラブル対策も紹介
面倒を見ることができないお墓、あるいは、将来的にお世話をする人がいなくなってしまうお墓にお悩みでしょうか?お墓と聞いてイメー…
2024年8月13日
-
永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説
こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…
2025年2月6日
-
墓じまいの手続きと必要書類がこれで分かる!手順と流れを解説
墓じまいとは、お墓を解体・撤去して墓地を管理者に返還するまでの一連の流れを言います。また、遺骨を現在のお墓から移動することを…
2023年7月19日