散骨の費用相場はどれくらい?散骨の方法別に解説します

今回の記事では、散骨の種類と費用について解説します。
目次
散骨とは

散骨とは火葬した遺体をパウダー状に粉砕して、粉末になった遺骨を海や山などの自然の中に撒く供養の方法のことを指します。
自分が亡くなったら自然の生命の循環の中に戻れるため、非常に人気なのです。
散骨の種類
まず散骨には以下のような種類があります。
海洋散骨

海洋散骨とは文字通り遺骨を海に撒く方法です。
ただし、海岸に行ってその場で遺骨を海に撒くことは、行政指導上NGです。
なぜならこのような散骨は沿岸漁業の漁師、沿岸で養殖をしている業者の障害になるからです。
日本海洋散骨協会のガイドラインでは、次のような自主ルールを設けています。
加盟事業者は、人が立ち入ることができる陸地から1海里以上離れた海洋上のみで散骨を行い、河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行ってはいけません。
これに則ると、散骨は海岸から1海里(1.852km)以上離れた海域で行う必要があります。
しかし、自分で船を用意して所定の場所選定して海に散骨するのは現実的には無理な話です。
したがって、海洋散骨をする際は、海上安全のためにも、専門業者を頼むのが無難です。
海洋散骨の専門業者は船をチャーターしていますし、散骨しても良い海域を把握しているので、ルールに沿った方法で散骨してくれます。
また海洋散骨の方法も、業者に散骨まですべて任せてしまう方法、複数の遺族で合同して船に乗り散骨をする方法、1家族だけで船をチャーターし散骨をする方法とあり、それぞれ料金が異なります。
山林散骨

海に遺骨を撒く海洋散骨に対して、山の中に撒く方法を山林散骨と言います。
山林散骨は海洋散骨以上に個人で実施するのが難しい埋葬方法です。
海は誰のものでもありませんから、条例や周辺環境に注意すれば散骨することができます。
対して、山林の場合は自分で所有している土地か、その土地を所有している人の許可を得た土地でしか散骨できません。
また仮に自己所有の土地でも、海洋散骨と同じく、近隣住民に迷惑がかかる場所での散骨はルール違反です。
つまり誰にも迷惑の掛からない山奥の自分の土地を持っていないと山林散骨はできないのです。
その点、山林散骨を扱っている専門の業者であれば、条件に合致した土地を用意していますから、やはり山林散骨の場合も業者に頼んだ方が良いでしょう。
その他の散骨

そのほか最近人気の散骨方法には、セスナ機などで上空か散骨する空中散骨や、カプセルに入れた遺骨をロケットに載せて飛ばし、成層圏で散骨する宇宙散骨などもあります。
散骨の費用
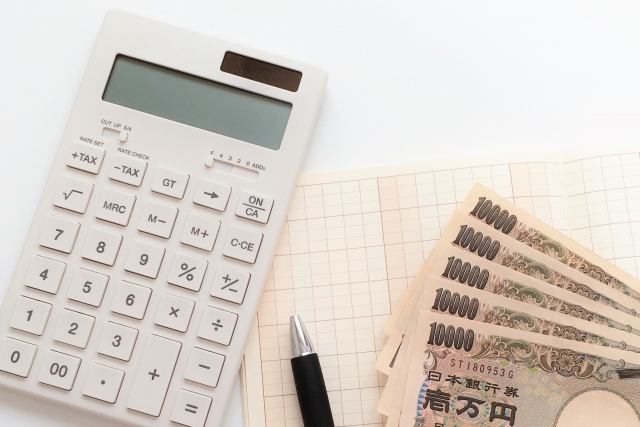
では散骨にはどのような費用がかかるのでしょうか。
その費用の内訳に沿って解説します。
散骨そのものの費用
散骨そのものの費用は、種類やプランによって、それぞれ以下のようになります。
| 1家族が単独で船を利用 | 15~30万円程度 |
| 複数の遺族合同で散骨 | 10万円前後 |
| すべてを業者に委託(関東) | 5.5万円~ |
| すべてを業者に委託(関西) | 8.8万円~ (合同委託専門業者の場合は3万円~) |
| 遺族が指定の場所で散骨 | 10万円前後 |
| 業者に全て委託 | 5万円前後 |
| 家族が単独でセスナ機またはヘリコプターを利用 | 20~30万円程度 |
| 業者に全て委託 | 30万円前後 |
粉骨の費用
散骨をするためには、遺骨をパウダー状に粉砕する必要があります。
粉骨の費用は、業者が手作業で行う方法と、機械で行う方法があり、前者の方が高額です。
どちらの場合も、作業量は遺骨の多さに比例するので、遺骨を収蔵する骨壺が大きければ高くなります。
| 2寸 (直径6~7cm×高さ7~8m) |
7,000円程度 |
| 3寸 (直径9.5cm×高さ11cm) |
10,000円程度 |
| 4~5寸 (直径12.5~15.5cm×高さ14.4~高さ17.5cm) |
17,000円程度 |
| 6~7寸 (直径18.2~21.7cm×高さ20.5~25.5cm) |
23,000円程度 |
散骨業者のルールに則るには遺骨を直径2mm以下に粉砕する必要があります。
粉骨は自分でもすることができますが、精神的にも体力的にも想像以上に大変です。
やはり業者に頼んだ方が無難でしょう。
乾燥、滅菌費用
遺骨は骨壺に入れたままにしておくと湿ってきます。
湿っている遺骨は粉骨機で粉骨できないため、前作業として乾燥させる必要があります。
特にすでに埋葬している遺骨を取り出して、散骨として改葬する場合はこのステップが必須です。乾燥費用も遺骨の量によって異なります
| 骨壺5寸以下 | 6,000円程度 |
| 骨壺6寸以上 | 12,000円程度 |
さらに遺骨の中に土が混ざっていると分別も行わなければならないため、その費用としてもだいたい20,000円かかります。
手元供養品の費用
散骨の場合、全ての遺骨を撒いてしまうと遺族の手元には故人を偲ぶものが何一つ残りません。
それが寂しいと思う場合は、遺骨の一部を手元に残す手元供養を行うことがおすすめです。
手元供養にもいろいろと方法がありますが、最もポピュラーなのは小さな骨壺を用意して遺骨をその中に入れ、自宅の棚の上などに安置する方法です。さらに骨壺も単に単に小型化したものから、インテリアとしても飾れるようなデザインのものまでいろいろ揃っています。
小さな骨壺の費用は、一般的な骨壺を小型化しただけのものであれば500~1000円です。
これにデザインが施されているものの場合は、1万~7万円前後です。
骨壺に遺骨を入れて手元供養するほかに、遺骨をペンダントに加工して常に身に着けて供養することを選ぶ人もいます。
この場合、ペンダントにはシルバー、ゴールドなどからステンレス、ガラスなどを素材にしたものまで多彩に用意されていて、それぞれ値段が違います。一般的な相場として数千~5万円前後です。
ペットの散骨と費用

近年では、ペットの火葬や散骨を専門に扱う業者が現れてきました。
人間の散骨を行う業者もペットに対応しているところがあります。
ペット散骨は、船をチャーターして自ら散骨するか、散骨すべてを業者に委託するかで大きく費用が異なります。
| 1家族が単独で船を利用 | 7~30万円程度 |
| 複数の遺族合同で散骨 | 10~16万円前後 |
| すべてを業者に委託(関東) | 1~5万円前後 |
葬儀社がペット散骨の事業を行っている場合は、ペットの葬儀・火葬とセットで散骨費用が安くなることがあります。
散骨に行政手続きは不要
散骨をするにあたって、行政機関に対しての手続きなどは必要ありません。
しかし、業者に散骨を依頼する場合は、散骨業者との間に契約書を取り交わす必要はあります。
散骨は違法ではない?

ここで気になるのは、そのような供養の方法は日本では法律違反にはならないのか、という点です。
散骨は法律上グレーゾーン
散骨は法律上あいまいな立ち位置にありますが、黙認されているのが現状です。
散骨には規制法が無く、既存の墓地や遺骨に関する法律である「墓地、埋葬に関する法律」(以下、墓埋法)にも明文規定がありません。
刑法190条の死体損壊等に違反するとの見方もありますが、法務省の「問題ない」とする非公式見解を経て、現状では黙認されています。
これに関しては、墓埋法などの研究者である田近 肇 氏が次のように説明しています。
現在、散骨という葬法がありうることはわが国でも広く認識されているということができるが、その先駆けとなったのが、平成3年10月に「葬送の自由をすすめる会」によって相模湾で実施された散骨である。それ以前、散骨は、遺骨を遺棄する行為として、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得」する行為を禁じる刑法190条に反し違法だとする見解もあった。しかし、同会は、散骨の実施に合わせて、法務省から、「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」との見解を引き出すことに成功した。
(中略)
「国としては、厚生労働省も法務省も文書による公式見解は出していないが、散骨葬については黙認しているというのが実状」というべきであろう。
散骨が違法になる事例
散骨は、実施方法によっては法律に違反することになります。
墓標を立ててしまう
墓埋法で「お墓」とは「墓標が立っているもの」だと解釈されています。
したがって、自分の家の庭に遺骨を撒いても法律違反にはなりませんが、しかし、撒いた場所へ記念に木を植えてしまうと、その木は法律上墓標だと判断されてしまいます。
墓標がある以上そこは墓地だと認定されるので、法律で許可を受けていない墓地を設けたということで法律違反になってしまうのです。
遺骨を粉末状にしないで散骨する
散骨業者の自主規制では、散骨する際は遺骨を直径2mm以下の粉末状にすることとしています。
遺骨を粉末状にすることを、粉骨と言います。
粉骨をせずに、遺骨をそれと分かる状態で散骨してしますと、死体遺棄罪に問われる可能性があります。
墓地以外で遺骨を埋める
散骨は自然葬の一種ですが、もう一つの自然葬の方法である「樹木葬」は、墓地でしか行えません。
墓地とは、行政に墓地経営を許可された区域を言います。
墓埋法では、遺骨の埋葬は墓地以外で行ってはならないとされているため、もし墓地でない山や庭に遺骨を埋めてしまうと、明確に違法になります。
このことは、墓埋法では下記のように定められています。
第2条
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
参考:墓地、埋葬等に関する法律
したがって、樹木葬をしたい場合は、樹木葬を取り扱っている墓地を探さなければなりません。
散骨は誰がする?
先ほども少し触れましたが、散骨は個人で行うといろいろなハードルがあります。
しかし越えられないハードルではありません。
散骨は自分でしようと思えばできる埋葬方法です。
散骨は自分でもできる?その注意点

自分する場合には以下の点に注意しましょう。
遺骨は必ずパウダー状に
散骨は遺骨を遺骨だと認識できないくらいまで細かく砕く必要があります。
前述の通り、遺骨をそれと分かる状態で散骨すると、死体遺棄罪に問われる可能性があります。
ではどのくらいの粉末にすればよいかというと、法律では決まっていません。しかし散骨業者の自主規制では直径2mm以下とされているので、このルールに沿っておけば大丈夫でしょう。
粉骨する方法には、遺骨を袋に入れてハンマーで叩くか、数万円で粉砕機がレンタルできるのでそれを利用するかです。
また、火葬した遺骨には、発がん性物質の「六価クロム」が含まれています。
六価クロムは、火葬の際に炉の内部に使用されている耐熱ステンレスが高温になることで発生し、遺骨に付着します。
六価クロムは、市販されている六価クロム用の処理剤で無害化することができます。
六価クロム用の処理剤は、通販などで1Lあたり1000円ほどで販売されているので、個人で遺骨を粉末にする際は購入した方が良いでしょう。
遺骨のパウダー化のみを代行してくれる業者もあるので、パウダー化のみ依頼するというのも方法の1つです。
散骨場所の選び方に注意
散骨場所については、まず散骨予定地の条例で散骨が禁止されていないことを確認する必要があります。
さらに、行政指導では以下のところは避けるようにと言われています。
- 水源地付近や生活用水として利用される河川、湖、沼など
- 漁場、養殖場、防波堤など
- 公園や住宅地
- 観光地や観光ルート
また以上に抵触しないような自宅の庭・私有の田畑果樹園などでも、近隣の住民から見える場所に撒くのは避けましょう。
散骨業者や散骨代行サービスに頼む方法も
このように個人で散骨を行うのは非常に手間であり、大変です。
したがって、その手間を避けるには上でも説明したような、散骨の専門業者に依頼した方が良いでしょう。
ただし散骨業者にも優良なところから悪徳業者まであるので、業者選定には注意しましょう。
散骨の流れ
散骨の具体的な流れについて解説します。
1.親せきやお寺に相談する
まずは、関係者に相談しましょう。
親せきへの相談
散骨は、故人の親族に関係のある話です。
相談なしに散骨してしまうと無用なトラブルに発展してしまうことがあります。
また、今あるお墓を墓じまいして改葬する場合は、墓じまいをすることの許可も必要です。
本家の墓を墓じまいする場合は、関係者が多くなるので注意しましょう。
墓じまいをする
墓を持っていて、墓に入っている遺骨を散骨したい場合は、ここで墓じまいをします。
墓じまいについては、下記記事を参考にしてください。
https://ohaka-sagashi.net/news/hakajimai/
2.散骨業者を選定する
まずは、散骨業者を選定しましょう。
もちろん、自分で粉骨から散骨まで行うのは不可能ではありませんが、業者に依頼して行う散骨をおすすめします。
業者はネット検索で探すことができます。
自分に合ったエリアやプランの業者を見つけましょう。
3.遺骨を散骨業者に発送する
火葬またはお墓から取り出した遺骨を散骨業者にゆうパックで郵送します。
その他、佐川急便やヤマト運輸などの配送業者は遺骨を取り扱えません。
お墓から遠方に住んでいて、墓じまいに立ち会えない場合は、墓所の解体を依頼した石材店に散骨業者の住所を渡し、そのまま郵送してもらうとスムーズです。
4.遺骨を乾燥・粉骨する
散骨業者に届いた遺骨は、乾燥されたのちパウダー状に砕かれます。
粉骨に遺族が立ち会い、遺族自らの手作業で粉骨できる場合があります。
立ち会いたい方は、事前に粉骨に立ち会えるか確認してから依頼しましょう。
立ち会わずに完全に業者に委託して粉骨する場合は、機械で粉骨するため、費用が抑えられます。
5.遺骨を散骨する
粉骨が完了したら、別の日取りで遺骨を散骨します。
散骨の方法には、遺族が自らまく方法と、完全委託された業者がまとめてまく方法があります。
業者に完全委託する場合は散骨の立ち合いはしません。
業者によって散骨されたあとに、散骨したことを証明する書類や写真が郵送されます。
散骨のトラブル
散骨で起こりうるトラブルには、「親族とのトラブル」「散骨業者とのトラブル」があります。
親族とのトラブル
散骨は新しい葬送の形なので、すぐには受け入れられない方もいらっしゃいます。
そのため、親族に相談せず散骨を行ってしまい、トラブルが発生することがあります。
トラブルを防ぐために事前の話し合いが大切です。
悪質な散骨業者とのトラブル
散骨業者の中には悪質な業者もいます。
- 業者とのトラブルには以下のようなものがあります。
- 生前予約でお金を払った業者が消える
- 高額な手元供養セットを勧められる
- 遺骨をゴミとして遺棄された
悪質な散骨業者は、正式な事務所を構えずレンタルオフィスなどを利用しているところがあり、業者とコンタクトを取りたくても取れなくなることが考えられます。
悪質な業者を選ばないために、業者選びは慎重に行うべきでしょう。
散骨業者を選ぶときの3つのポイント
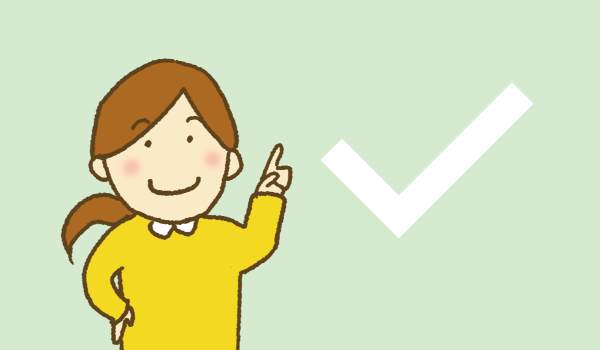
悪質な散骨業者に散骨を依頼しないためにチェックしておくべき3つのポイントをご紹介します。
1.価格が相場よりも極端に安いところは避ける
散骨の料金が1万円以下の業者は警戒が必要です。
ルールに則って散骨をする場合は、船をチャーターするなどどうしても費用がかかってしまうものです。
あまりに安い料金を提示してくる散骨業者は、ルールに則った散骨をしていない可能性があります。
例えば、遺骨を川に流してしまう業者がいます。
川やダムでは人々の健康を害する恐れがあるため、散骨をしてはいけません。
安すぎる業者には依頼しないようにしましょう。
2.電話やメールの対応がしっかりしているか
電話での対応が悪い、メールがすぐに帰ってこない業者も中にはいます。
そういった不誠実な業者に散骨を依頼してしまうと、故人を送るための散骨なのに業者の対応でストレスを感じてしまうかもしれません。
複数の散骨業者に問い合わせ、対応の良さを比較してみると良いでしょう。
3.複数の業者からパンフレットを取り寄せて比較しよう
後悔しない散骨をするために、複数の散骨業者に問い合わせてパンフレットを取り寄せましょう。
その際、料金がセット価格で表示されている場合は、粉骨の料金や遺骨を預けるときのスタッフの交通費が価格に含まれているのか確認しましょう。
一見安く見えても、粉骨などの料金が含まれていないため安いということもあります。
業者を選ぶときは、費用の総額やスタッフの対応を比べてみましょう。
散骨をして後悔してしまうケース
金銭的な負担が少なく、お墓と違って跡継ぎの心配がない散骨ですが、散骨をしてから後悔してしまうケースもあります。
遺骨すべてを散骨してしまい、故人と向き合う場所がない
遺骨を全部散骨した後に、故人と向き合う場所がないことに気づき後悔してしまうことがあります。
実は遺骨を全部散骨する人は少なく、一部手元にとっておく人が多いようです。
家族など身近な方の遺骨を散骨する場合は、後で後悔しないように一部手元に残しておきましょう。
親せきと十分に話をせず散骨してしまい、親せきとの関係が悪くなった
散骨する際は、故人と関わりのある親族にきちんと話をしてから行いましょう。
勝手に散骨すると、散骨を良く思っていない親族の反感を買ってしまう恐れがあります。
トラブルを避けるために、散骨が故人の願いであることなどを説明し、周囲に納得してもらうことが必要です。
まとめ
散骨によって自分を埋葬してほしいと思っている人にとっては、いろいろと明らかになったのではないでしょうか。
現在お墓を新たに買うと150万円以上かかります。
その点散骨なら高くても20万円程度ですから、費用の点でも遺族に迷惑をかけなくて済みます。
このことからも散骨は今注目されているのです。
散骨を考えている人はぜひ以上の解説を参考に、本当に実施するかどうかを検討しましょう。

お墓さがしは、ご希望にあったお墓を一括検索できる
日本最大級の霊園・墓地検索サイトです。
全国対応の墓じまい無料見積もりも承ります。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
TEL:0120-207-012

HP:https://www.reiseki.net/
住所:大阪府堺市堺区中向陽町1-6-1
加盟団体:日本海洋散骨協会
ご遺骨を加工してアクセサリーやオブジェを作成します。
海洋散骨も承ります。
散骨の費用相場はどれくらい?散骨の方法別に解説しますに関する記事
-
墓じまいとは?費用と流れを詳しく解説!トラブル対策も紹介
面倒を見ることができないお墓、あるいは、将来的にお世話をする人がいなくなってしまうお墓にお悩みでしょうか?お墓と聞いてイメー…
2023年7月19日
-
遺骨を加工してできる宝石やアクセサリーには何がある?
遺骨アクセサリーや遺骨の加工品は、手元供養品の一つとして普及しています。今回は、遺骨アクセサリーを始めとする遺骨の加工品につ…
2022年2月25日
-
遺骨がいらない場合はどうする?処分しなければならないときの対処法
故人に思い入れや愛情があれば遺骨は大事なものですが、一方でそういった感情が無ければ、扱いに困ってしまうことも現実にはあります。…
2023年4月24日
