墓じまいの手続きと必要書類がこれで分かる!手順と流れを解説
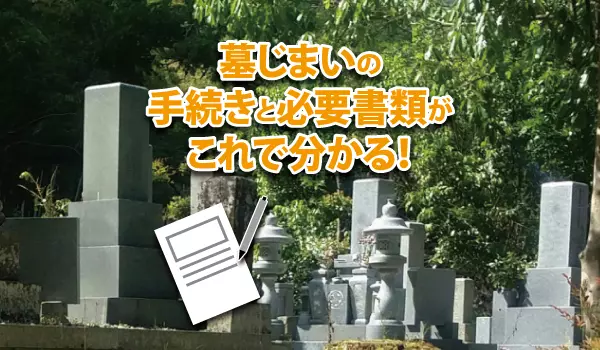
墓じまいとは、お墓を解体・撤去して墓地を管理者に返還するまでの一連の流れを言います。
また、遺骨を現在のお墓から移動することを、「改葬」と言います。
墓じまいをするには改葬が必要になりますが、改葬をするには、現在のお墓がある役所での行政手続きが必要になります。
この記事では、墓じまいにかかる手続きを詳しく解説します。
なお、墓じまい全般については、『墓じまいとは?』で解説しています。
目次
墓じまい全体の流れ
まずは、行政手続きを含めた墓じまい全体の流れを解説します。
墓じまいの流れは、以下のようになります。
1.お墓の名義人・親族に了承を得る
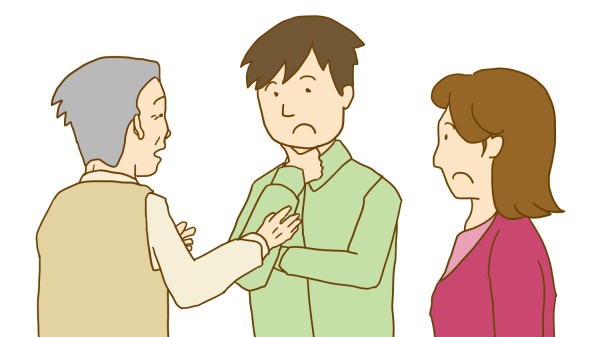
断りなく墓じまいをしてしまうと、後に不要なトラブルを招きます。
お墓の名義人ではないけどお参りに来てくれている方もいるかもしれません。また、本家の墓を墓じまいしようとして、分家筋からクレームが来ることもあります。
なお、墓じまいにあたってはお墓の使用者の承諾が必要です。一般的に、お墓の名義人になっている人がお墓の使用者です。
手続きでいうと、墓地の使用者と改葬手続きをする人が異なる場合は「承諾書」に署名・捺印してもらう必要があります。
2.現在の墓地管理者・お寺に相談する

- 民営霊園:管理事務所
- 公営霊園:管理事務所(なければ自治体役所)
- 共同墓地:墓地管理委員会
- 寺院墓地:お寺
現在の墓地管理者からは、手続きの際に署名・捺印をもらう必要があります。
事前に墓じまいの了承を得ておきましょう。
お寺以外にお墓がある場合
民営霊園や公営霊園の場合は管理事務所に、共同墓地の場合は墓地管理委員会に墓じまいしたい旨を伝えます。
通常、連絡先は現地の看板などで確認できます。
お寺にお墓がある場合
お寺にお墓がある場合は、特に丁寧に相談します。
お寺で墓じまいをするということは、檀家をやめることと直結します。
檀家とは、お寺に仏事全般の面倒を見てもらう代わりに、経済的にお寺を支える家のことです。
檀家の減少はお寺にとって死活問題になるので、そこを念頭に丁寧にお話しします。
まずは、墓じまいは決定事項ではなく、あくまでも相談としてお話します。
日頃お世話をしてもらっている感謝や、なかなか顔を出せなかったお詫びなども合わせて伝えましょう。
ここでお寺側の態度を硬化させると、高額な離檀料を要求されるなど、後々に不要なトラブルを招きかねません。
3.改葬先(遺骨の引っ越し先)を決める

手続きに必要な受入証明書は新しい墓地から発行してもらうので、改葬先が決まっていないと手続きができません。
お墓が遠いという理由で墓じまいする場合は、周辺のアクセスのいいお墓を買い求めましょう。
跡継ぎがいないと理由で墓じまいする場合は、永代供養墓を検討します。
永代供養墓とは、墓地を管理する後々までお寺がご遺骨の供養をしてくれるので、跡継ぎがいらないというお墓です。
費用を抑えるなら合祀墓が良いでしょう。そのほか、樹木葬や納骨堂などもあります。
4.墓石の解体工事をする石材店を決める
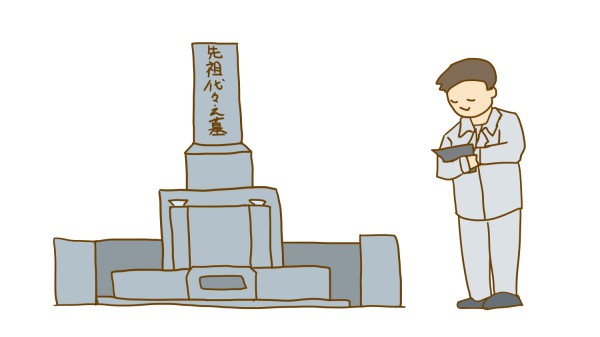
手続きにあたって業者から発行してもらう書類はありませんが、申請の際に業者の情報を記載しなければならない自治体もあります。
業者の見当を付けたら、まずは見積もりを取ります。
見積もり前に契約すると、思ってもみなかった金額になることがあるので注意しましょう。
民営霊園の場合は指定業者がいるので、管理事務所に墓じまいの相談をした時に一緒に業者も紹介してもらいます。
寺院墓地でも指定石材店がいることがあります。
公営霊園、共同墓地、指定石材店のいない寺院墓地の墓じまいをするときは、自分で業者を選びます。
墓地の近場で、かつ墓地での施工実績のある石材店を選ぶと安心です。
指定業者がいなければ複数に見積もりを頼む相見積もりができます。
費用に納得いかなければ、他の石材店にも見積もりを依頼しましょう。
5.自治体の役所で行政手続きをする
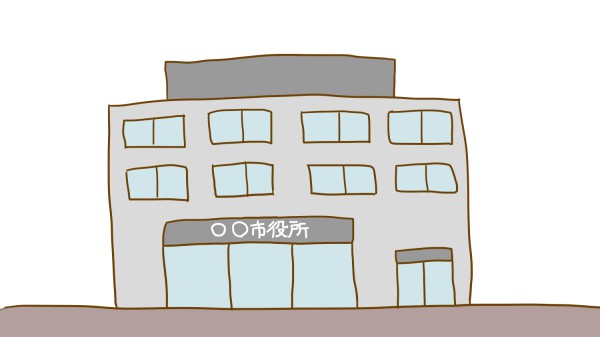
内容は、「改葬許可証」を交付してもらうための、「改葬許可申請書」と必要書類の提出です。
詳しくは、後述の以下をご覧ください。
6.閉眼法要をする

閉眼法要とは、お墓の故人の依り代としての機能を停止させる儀式で、内容としてはお坊さんに墓前で読経してもらうことです。
魂抜き、性根抜きなどとも呼ばれます。浄土真宗の場合は遷仏法要(せんぶつほうよう)と言います。
依頼先は、日ごろからお世話になっているお寺があればそこに依頼します。
いなければ、墓地の近くで家の宗派と一致するお寺に問い合わせたり、ネットの僧侶派遣サービスを使って手配します。
なお、閉眼法要は墓石解体工事の当日にする必要はなく、工事の1週間くらい前に済ませてしまう人も多いようです。
また、閉眼法要の時に遺骨を取り出すわけではないので、手続き完了前に済ませても構いません。
7.墓石の解体工事をして墓地を返還する

墓石を更地にして墓所に返還します。
ここで墓じまいは終了です。
取り出した遺骨は現地に引き取りに行くか、石材店に改葬先に発送してもらいます。
8.遺骨を改葬先に納骨する
墓じまい後、遺骨を改葬先(新しいお墓)に納骨します。
これで「改葬」が完了します。
納骨の際は「改葬許可証」が必要になるので、持参しましょう。
墓じまいの行政手続きに必要な書類
段取りが整ったら、墓じまいの手続きをします。
墓じまいに必要な書類は、以下の通りです。
| 書類 | 発行元 |
| 改葬許可申請書 | 墓のある自治体役所 |
| 埋蔵(埋葬証明書)または署名・捺印 | 墓地管理者 |
| 受入証明書 | 遺骨の引越し先 |
| 承諾書 | 墓地の名義人 |
| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者 |
改葬許可申請書
改葬許可申請書は、改葬許可証の交付を申請する書類で、現在の墓地がある自治体役所で配布しています。
改葬許可申請書はどこの自治体でも必要な書類です。
役所の窓口(環境衛生課、市民生活課など)またはHPから入手できます。
埋蔵(埋葬)証明書または署名・捺印
埋蔵(埋葬)証明書は、現在の墓地に誰が埋葬されているのかを証明する書類で、現在の墓地の管理者から発行してもらいます。
民営霊園や公営墓地なら管理事務所、寺院墓地ならお寺から発行してもらいます。
ただし、埋蔵(埋葬)証明書の代わりに改葬許可申請書への署名・捺印でOKな場合もあります。
自治体のHPまたは窓口で確認してみましょう。
受入証明書
受入証明書は、墓地の契約を証明する書類で、新しい墓地(改葬先)の管理者が契約時に発行します。
受入証明書が必要か否かは、自治体によって異なり、改葬許可申請書に墓地名を記入すればOKなこともあります。
自治体のHPで確認してみましょう。
承諾書
承諾書は、墓地の使用者(墓地の名義人)と、改葬許可申請をする人が違う場合に必要です。
承諾書のテンプレートは墓地のある役所で配布されています。窓口またはHPから入手しましょう。
墓地の使用者は改葬許可申請をする場合は不要です。
申請者の身分証明書写し
改葬手続きには書類を提出する人の身分証明書が必要なことがあります。
墓地の使用者ではなく、申請者の身分証明書である点に注意しましょう。
身分証明書が必要かどうかは自治体によって異なります。
墓じまいの行政手続きの流れと手順
お墓のある自治体役所で必要な、「改葬許可申請」の流れを紹介します。
役所から「改葬許可証」が出て初めて遺骨を取り出すことができるようになるので、遅くとも墓石の解体工事に取り掛かる前までに手続きを完了してください。
1.自治体から「改葬許可申請書」を入手する
改葬許可申請書は、現在の墓地がある自治体の役所で発行されています。
実際に窓口に行っても入手できますが、多くの場合は自治体HPからダウンロードできるようになっています。記入する内容は、下記のような事項があります。
あくまでも一例なので、記入する内容は自治体によって異なります。
改葬許可申請書の記入内容の例
- 申請者の署名・捺印
- 埋葬されている人の情報(氏名、没年月日、火葬場など)
- お墓の使用者と埋葬されている人の続き柄
- 改葬の理由
- 改葬先の墓地
- 解体工事をする業者の名前
特に埋葬されている人の情報については、分からないところもあるかと思います。
分からないところは「不明」と記載すれば概ね大丈夫です。自治体の記入のルールに従ってください。
多くの場合郵送でやり取りできるので、遠方に住んでいる人はHPから改葬許可申請書を印刷し、記入して役所に送付する形が良いでしょう。
2.現在の墓地管理者から「改葬許可申請書」に署名・捺印してもらう
一通り記入したら、改葬許可申請書を持って墓地管理者の所に行きます。
遠方に住んでいれば、郵送で受け取ってもらえるかを管理者に確認しましょう。墓地の管理者には、改葬許可申請書に署名・捺印をしてもらいます。
自治体によっては、署名・捺印ではなく「埋蔵(埋葬)証明書」が必要なこともあります。
署名・捺印をしてもらったら、返送してもらいましょう。
これで改葬許可申請書の記入は完了です。
3.改葬先から受入証明書をもらう
役所の改葬許可の手続きでは、改葬許可申請書の他にいくつか書類が必要です。
改葬先のお墓を契約したら、新しい墓地の管理者から「受入証明書」が発行されます。
受入証明書の写しを用意して、申請書と一緒に提出します。
4.お墓の使用者から承諾書に署名・捺印してもらう
承諾書は、現在の墓地の使用者と改葬許可申請が異なる場合のみ必要です。
墓地の使用者とは、墓地に名義人として登録されている人のことを言います。承諾書のテンプレートは墓地がある役所の窓口やHPからダウンロードできます。
現在の墓地の使用者に署名・捺印してもらいましょう。
5.書類一式を役所の窓口に提出する
改葬許可申請書、受入証明書、承諾書がそろったら、身分証明書のコピーをつけて役所に提出します。
遠方に住んでいたら、返送用封筒をつけて郵送でも構いません。
6.「改葬許可証」が交付されて手続き完了
書類が受理されたら、「改葬許可証」が発行されます。
書類を提出してすぐに発行されるとは限らないので、書類は工事より余裕をもって提出しましょう。改葬許可証が発行された時点で、墓地から遺骨を移動できるようになります。
また、改葬許可証は新しい墓地に納骨する際にも必要になるので、なくさずにとっておきましょう。
墓じまいの費用はどれくらい?

墓じまいの費用相場は、以下のようになっています。
ただし、お墓の立地や広さ、造りによって、相場の倍以上の金額がかかることもあります。
- 墓石解体費用:20~30万円(8~10万円/㎡)程度
- 閉眼法要のお布施:1~5万円程度
- 離檀料(寺院墓地のみ):1~20万円程度
これとは別に、遺骨の引越し先の費用が掛かります。
費用相場は以下の通りです。
- 墓石のお墓(新規建立) :100~250万円
- 永代供養(納骨堂) :30~100万円
- 永代供養(樹木葬) :10~70万円
- 永代供養(合葬墓): 3~30万円/1人
- 散骨: 3~30万円/1人
- 送骨: 1~10万円/1人
詳しくは、以下のコラムをご覧ください。
【参考】墓じまいとは?費用と流れを詳しく解説!トラブル対策も紹介
墓じまいの手続きQ&A
一般的なケースであれば書類をもらって各方面に署名・捺印をもらうだけで手続きできるのですが、イレギュラーなケースでは手続きが難航することもあります。
ケース別の改葬手続きについて解説します。
まとめ
墓じまいの手続きについて解説しました。
墓じまいには現在の墓地がある市区町村の役所で手続きが必要です。
分からないことや、特殊なケースの場合も、役所の窓口に行けば相談に乗ってくれます。
手続きには現在の墓地管理者、改葬先の墓地管理者、墓地の使用者の三者の承諾が必要です。
手続きに入る前に事前に了承を得ておきましょう。
また、申請書類に解体業者の情報を書く場合もあるので、工事をする石材店も先に決めておきましょう。
墓じまいの見積もりサービスに相談してみよう
お墓さがしでは、墓じまいの見積もりサービスを行っています。
お見積り・ご相談を完全無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
墓じまいの手続きと必要書類がこれで分かる!手順と流れを解説に関する記事
-
墓じまいとは?費用と流れを詳しく解説!トラブル対策も紹介
面倒を見ることができないお墓、あるいは、将来的にお世話をする人がいなくなってしまうお墓にお悩みでしょうか?お墓と聞いてイメー…
2024年8月13日
-
永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説
こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…
2025年2月6日
-
墓じまいの費用は誰が払う?払えない場合はどうする?
墓じまいをするには、おおおそ20~30万円の費用がかかると言われています。墓じまいをするにあたって、「墓じまいは誰がすればい…
2023年7月19日
墓じまいの手続きに関するよくある質問
-
墓じまいには、どんな手続きが必要ですか?
お墓のある自治体の役所で、「改葬許可申請」という手続きが必要です。郵送などでも手続きできます。
-
墓地の管理人が分からないのですが、どうすればいいでしょうか?
現地で連絡先が書かれている看板などが発見できなければ、墓地のある自治体役所に相談します。

経歴
2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。