遺骨は自宅安置しても大丈夫?お骨を保管する際の注意点
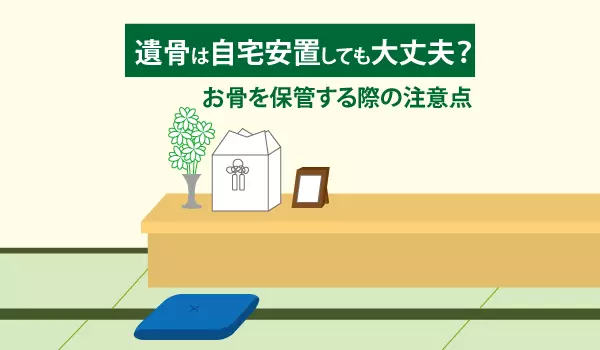
亡くなっても大切な人と離れがたく、納骨をせずに、遺骨を自宅に安置したいという方も少なくありません。
この記事では、自宅で遺骨を管理する方法と、注意点を解説します。
目次
法律ではずっと自宅供養してもOK

自宅に遺骨を安置しておくことは違法ではありません。
法律では、故人の遺骨をいつまでに納骨するかについて規定していません。
ただし、庭先などの墓地でない所に遺骨を「埋める」ことは、刑法の「死体遺棄罪」に該当します。
お墓に関しては、「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、墓埋法(ぼまいほう))などの法律で定められています。
墓埋法では、遺骨の埋葬先について以下のように定められています。
第1条 5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
遺骨の保管方法
自宅で保管をする際、何か特別な用意は必要なのでしょうか。
ここでは、大まかな遺骨を自宅安置する方法を分類します。
全ての遺骨を骨壺などで安置

故人の遺骨をすべて自宅に安置します。
一般的には、火葬場から自宅に持って帰ったままの状態で、骨壺で保管します。見た目が気になる方には、自宅安置用の骨壺や仏壇もあります。
リビングにおいても馴染む、おしゃれなデザインのものが多いです。なお、全骨をコンパクトに安置したい場合は、遺骨を粉状に砕く「粉骨」をしてから、小さな入れ物で保管することもあります。

一部の遺骨を小さな入れ物やアクセサリーに保管する

遺骨を分骨し、一部はお墓に納骨するか散骨して、残りの一部の遺骨を自宅に安置します。
お骨は小さな骨壺やオブジェ、アクセサリーなどに入れます。
アクセサリーやごく小さな入れ物であれば、持ち歩いたり身に着けたりすることもできます。
分骨は、火葬の際に一部を取り分けるか、一度お墓に入れたものを取り出すかどちらかが考えられますが、一般的には火葬のタイミングで分けます。
なお、「分骨すると故人があの世で五体満足になれない」などの迷信が気になる方もいるかもしれません。
これは気の持ちようとしか言えませんが、少なくとも仏教のお釈迦さまもやキリスト教の聖人も分骨されているので、多くの場合で宗教的には問題ないでしょう。
遺骨加工品のオブジェなどを作る

故人の遺骨からオブジェを作成するサービスもあります。
水晶などの置物、プレート、宝石など、様々な形になります。
宝石になったものはアクセサリーとして加工され、身に着けることもできます。
遺骨は粉状にしたり融解させることでオブジェに混ぜられるそうです。お骨がそのまま残らないと寂しい反面、来客があった時に違和感なく飾っておけるのが利点です。

遺骨の置き場所


火葬場から遺骨を持ち帰った際、後飾りの祭壇をつくり、そこに骨壺を安置します。
祭壇は四十九日を過ぎると解体するのが通例です。
それでは、その後は遺骨はどこに置くのが良いのでしょうか。
仏間や仏壇の側に遺骨を置く
四十九日までの後飾りの祭壇も仏間に置くので、遺骨も仏間や仏壇に置くのが馴染むでしょう。
実際、遺骨を収納するスペースがついている仏壇も販売されています。
全骨で骨壺のまま安置するとなると、仏壇では厳しいので専用の台などを用意しましょう。
なお、本来仏壇は信仰の中心である本尊を祀るものなので、遺骨を仏壇に置くのは宗教上適切ではないとされています。
仏教はお寺の本堂のミニチュア版です。お寺の本堂に遺骨を置かないのと同様、仏壇にも本来は遺骨を置きません。
後飾り祭壇をそのまま使う
一般的には四十九日後は処分しますが、後飾り祭壇をそのまま自宅安置用のスペースとして利用するケースもあります。
遺骨は、四十九日法要が終わるまでは、自宅に後飾り祭壇を設けてそこに飾ります。
後飾り祭壇とは、骨上げ後のお骨を祀る祭壇などのことで、白い布がかけられた台にロウソクや香などのお供えとともに、遺骨を祀るものです。
リビングなどに供養スペースを設ける
リビングなどに専用のスペースを設けて安置します。
おしゃれな骨壺や遺骨の加工品サービスを利用したものであれば、小物として飾ることができます。
また、納骨スペースがついている仏壇にはモダンなデザインのものもあります。
椅子や机など洋風なデザインの家具と並べても、違和感なく設置できます。
自宅安置の注意点


自宅で安置するにはそれなりの管理も必要です。
寂しい気持ちにおされて何となく自宅に置いていたけど、トラブルが起こってしまった!
そうなる前に、遺骨を管理する際の注意点を見ていきましょう。
湿気注意!遺骨にカビが付くことがある
遺骨にカビが付くことは多い事例ではないものの、水分や栄養素などの一定の条件が揃えばカビは繁殖します。遺骨の保管には、以下の点に注意してください。
遺骨の自宅安置の注意点
- 湿気をできるだけ避ける
- 結露に気を付ける
- 遺骨と周囲の衛生を保つ
なお、これらの方法は100%遺骨にカビが生えないことを保証するものではありません。
火葬した時点での無菌状態から時間が経てば、カビが生えるリスクも高まります。
遺骨を自宅で安置する場合は、置いておく期間や納骨のタイミングも考えておいた方が良いでしょう。
湿気をできるだけ避ける
骨壺は密閉されているように見えて、実はふたと入れ物の間に隙間があります。
外気温が変われば入れ物のとの温度差で外気流れ込み、水分や菌が侵入します。
ふたと入れ物はテープなどで密閉しておきましょう。
また、桐箱に入れておくことで、箱がある程度水分を吸ってくれます。
場所がないからと言って、押入れの奥や水回りには絶対に置いてはいけません。
結露に気を付ける
気温の変化で骨壺の中が結露し、水分がついてしまうことがあります。
久しぶりに骨壺を開けたら底に水がたまっていたというケースすらあります。
シリカゲルなどの吸湿剤を一緒に入れることで、ある程度予防できます。
湿気は底にたまるので、吸湿剤も底のに入れましょう。
遺骨と周囲の衛生を保つ
遺骨は800℃~1000℃の高温で焼かれるので、骨壺に入る時は無菌の状態です。
ですが、その後骨壺の蓋を開けたり、素手で遺骨に触れると、菌やその餌となる汚れが入り込むことがあります。
また、先述のとおり骨壺は外気を吸うので、周りにカビたものを置くと、カビがそのまま入りこむかもしれません。
遺骨には触れず、周囲の衛生環境にも注意してください。
周囲の反対
親戚など、周囲の考えによっては、「遺骨は土に還すものだ」「納骨しないと成仏できない」などと自宅安置に反対されることがあります。
また、故人とそれほど深い付き合いのない来客があった時、遺骨が側にあることに違和感を感じる人もいます。
どういった形で自宅に置くのか、どこで管理するのかなどは身近な人と話しておきましょう。
いつかは自宅に置けなくなる
自宅で供養している本人が亡くなってしまったら、安置されていた遺骨はどうなるのでしょうか。
供養していた方の子どもが引き継ぐのでしょうか。
それでは、子供が遠方に住んでいたり、いなかった場合は?
大抵の場合、供養する本人がいなくなると、それまで自宅に安置されていた遺骨は行き場を失います。
孤独死の現場の遺品整理をしたら、仏壇の下から遺骨が出てきたという事例もあります。
「とりあえず側に置いておく」では、供養する本人に万が一のことがあった時に遺族が困ってしまいます。
納骨はいつするのか、納骨先はどこにするのかについて、事前に家族で話し合っておきましょう。
最終的な遺骨の行き先
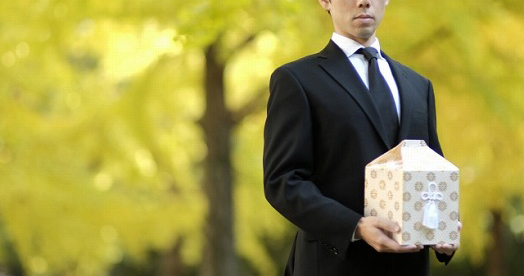
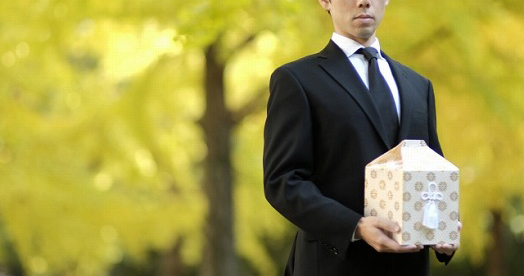
最終的に、遺骨は自宅以外の所に行きつきます。
家のお墓があり、跡継ぎがいる方であれば、そのまま先祖代々の墓に入れることで落ち着くでしょう。
しかし、今お墓がない場合や、跡継ぎがいない場合はどうすればいいのでしょうか。
ここでは、最終的な遺骨の納骨先について紹介していきます。
一般的なお墓を建てる場合
一般的な、墓石のあるお墓を建てる場合、費用も期間もある程度掛かります。
規模や条件にもよりますが、費用の相場は150~300万円、期間は2~3カ月が目安となります。
また、一般的なお墓を扱っている霊園はかなり多く、選択肢も広がります。
交通アクセスや墓地の種類、設備、費用など諸条件を勘案して決めましょう。
跡継ぎがいない場合
跡継ぎがいない場合は、「永代供養」付きのお墓を選ぶのが妥当でしょう。
「永代供養」付きのお墓では、跡継ぎのないお骨でも、お寺などの墓地管理者が、永代にわたって供養してくれます。
永代供養墓には、以下のようなものがあります。
樹木葬


納骨堂


合葬墓・合祀墓



お金がない場合の供養の方法
お金がなくて遺骨を供養できない場合は、以下のような費用を抑えられる供養の方法を検討しましょう。
合葬墓・合祀墓に入れる



散骨する


送骨サービスを利用する


まとめ
自宅で遺骨を安置することは、法的には何ら問題ありません。
全骨あるいは分骨で管理し、様々な入れ物や形で安置されます。
骨壷のまま安置することも当然ありますが、近年ではおしゃれな入れ物やオブジェなどが数多くあります。
また、遺骨を加工して宝石や置物にするというサービスも登場しています。
しかし、自宅での遺骨管理には注意も必要です。
遺骨は湿気に弱く、カビることがあります。
また、親族の反対や、いつかは自宅に置いておけなくなるという問題もあります。
遺骨を側に置いておきたい場合は、しっかり家族と話し合い、保管のスタイルや納骨のタイミングなど、しっかり話しておきましょう。
また、納骨先を決めておくことも重要です。
供養する本人に万が一のことがあっても、遺族が困らないようにお墓も決めておきましょう。



※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
遺骨は自宅安置しても大丈夫?お骨を保管する際の注意点に関する記事
-
遺骨は納骨しないで家に置いていてもいい?納骨しない供養も紹介
日本の慣習に従えば、遺骨は四十九日に納骨することが一般的です。四十九日にお墓が間に合わなければ、一周忌や三回忌法要に合わせて…
2025年2月6日
-
自宅墓とは?種類や費用を解説!メリット・デメリットは?
近年では散骨や樹木葬などの新しい供養の方法が広がり、従来のような墓石のお墓に納骨することはもはや常識ではなくなってきました。…
2024年6月3日
-
【インタビュー】自宅墓:お墓を自宅に置ける「棲家」
大切な人とお別れすることは、誰にとっても寂しいものです。故人と離れがたく、なかなか納骨をする決心もつかないのではないでしょうか…
2024年6月3日
遺骨の自宅安置に関するよくある質問
-
遺骨は自宅に置いていても良いのでしょうか?
問題ありません。納骨の期限などについても、法律での決まりはありません。
-
遺骨を自宅安置する際に、気を付けることはありますか?
ごくまれに遺骨にカビが生えることがあるので、風通しが良い所、結露を避けるために温度差の少ない所に安置してください。
