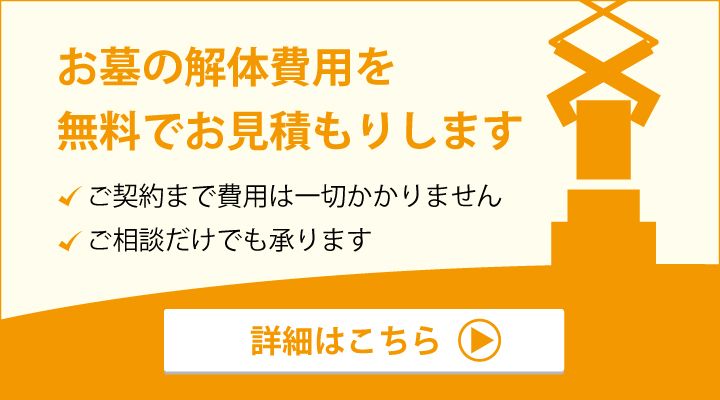墓じまいはどのような手順で行う?必要な手続きや注意点

少子化や核家族化が進む昨今、家のお墓を墓じまいし、永代供養墓に遺骨を移す方が増えています。
墓じまいしたいけれど、何から手を付けていいのかわからないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の記事では、墓じまいの手順や流れについて解説します。
目次
墓じまいの基本的な流れ
墓じまいは基本的に以下の流れで行われます。
1.墓じまいに必要な書類を確認する
2.お墓の関係者に相談する
3.遺骨の移し先を決める
4.墓石の撤去工事を依頼する石材店を決める
5.役所で改葬許可証を交付してもらう
6.僧侶に閉眼法要を依頼する
7.石材店が墓石の撤去工事を行う
8.用意しておいたお墓に遺骨を納骨する
1.墓じまいに必要な書類を確認する
今あるお墓を墓じまいして、遺骨を別の墓地へ移す際には、現在の墓地がある市区町村での行政手続きを経て、「改葬許可証」を交付してもらう必要があります。
まずは、墓地がある自治体のHPや役所で、必要書類を確認します。
「改葬許可証」の交付に必要な書類を表にまとめました。
| 書類名 | 書類の意味 | 発行元 |
| 改葬許可申請書 | 遺骨を他の墓地や納骨堂に移す許可を得るために提出する書類 | 市区町村の役所または自治体HP |
| 死亡者の戸籍(除籍)謄本 | 申請者と死亡者との関係を確認するために必要な書類 | 市区町村の役所 |
| 埋葬(埋蔵)証明書 | 現在使用している墓地等に遺骨が埋蔵・収蔵されていることを証明する書類 | 現在の墓地 |
| 墓地使用許可証(永代使用許可証) | 現在の墓地使用者を確認するために必要な書類 | 新しい墓地 |
| 受け入れ証明書 | 遺骨の移し先の墓地管理者が、遺骨を受け入れることを証明する書類 | 新しい墓地 |
| 承諾書 | 墓地使用者と申請者が異なる場合に、墓地使用者の承諾を得ていることを証明する書類 | 既存墓地の使用者 |
| 申請者の身分証明書写し | 申請者の身分を証明するための書類 | 申請者 |
基本的には上記の書類が必要になりますが、改葬手続きの対応は自治体によって異なります。
取り出した遺骨を自宅に置いておく場合や散骨する場合は、改葬許可の手続きは不要です。
ただし、自宅で保管していた遺骨をさらに他の墓地や納骨堂へ移す際には、改葬許可の手続きが必要になりますので注意しましょう。
2.お墓の関係者に相談する
必要書類を確認できたら、次に親族や墓地管理者と墓じまいの相談をしましょう。
事前に相談しておくことで、墓じまいを円滑に進めることができます。
親族への相談
法律上、墓じまいの決定権はお墓の承継者にありますが、家墓の墓じまいは親族全体に関わることなので事前相談が必須です。
お墓の承継者が独断で墓じまいを進めたことがきっかけで、トラブルになったケースもあります。
もちろん、墓じまいをする人がお墓の権利者でない場合、または親族で共有している場合は、勝手に墓じまいをすることはできません。
その場合は、お墓の権利者の承諾書が必要になります。
承諾書のテンプレートは、役所や自治体のHP等で配布されていますので、事前に取得しておくとスムーズです。
墓地管理者への相談
次に、墓地の管理者に墓じまいについて相談をしましょう。
寺院墓地ならお寺、霊園なら管理事務所に行きます。
公営や民営の霊園にあるお墓の墓じまいでは、おおむねスムーズに話を進めることができるでしょう。
一方、お寺に墓じまいの相談をする場合は、伝え方に少し配慮が必要です。
お寺にとって墓じまいは、檀家を失うことを意味します。
今までお世話になった感謝と、墓じまいせざる得なくなった事情をしっかりと伝えましょう。
話がまとまったら、「埋葬(埋蔵証明書)」の発行と、「改葬許可申請書」に署名捺印をしてもらいます。
3.遺骨の移し先を決める
お墓から取り出した遺骨をどこに移すかを決めます。
遺骨の移し先として多く選ばれているのは、永代供養墓です。
永代供養墓とは、遺族に代わって墓地の管理者がお墓の管理や遺骨の供養を行うお墓です。
墓じまいの理由として多くあげられるのは、「後継ぎの不在」なので、改葬先にはお墓の承継を前提としていない永代供養墓がおすすめです。
一口に永代供養墓といっても様々な種類があります。
永代供養墓として代表的な、合祀墓、樹木葬、納骨堂を紹介します。
合祀墓
他の永代供養墓に比べ、非常に安く納骨できるため、改葬先として人気があります。
費用相場は、3~30万円程度です。
近くの合祀墓を探す >
樹木葬
1区画を1~4名で使用するタイプが多く、両親など近い親族の遺骨を改葬する際によく選ばれています。
費用相場は、10~80万円程度です。
近くの樹木葬を探す >
納骨堂
ロッカー式やマンション型がなどの種類があり、少人数で使用するものだけでなく、家のお墓として使用できるものもあります。
費用相場は、40~150万円程度です。
近くの納骨堂を探す >
遺骨の移し先が決まったら、その墓地の管理者に「受け入れ証明書」を発行してもらいます。
4.墓石の撤去工事を依頼する石材店を決める
墓石の撤去工事を行う石材店を決めます。
工事費用の見積もりは無料で出してもらえるので、可能なら複数社で相見積もりを取りましょう。
ただし、民営の霊園や寺院墓地では、工事ができる業者が指定されていることがあります。
この場合、基本的に他の石材店で相見積もりを取ることはできません。
墓地の管理者に墓じまいの相談をする際に、石材店をこちらで選んでよいのかを確認しましょう。
市や都などの自治体が運営する墓地や古くからある村墓地などでは、業者が指定されていないことがほとんどです。
5.役所で改葬許可証を交付してもらう
お墓から遺骨を取り出す前に、現在の墓地がある自治体役所にて、行政手続きを行います。
遺骨を他の墓地に移す際には、自治体の市区町村長に改葬許可申請を行い、改葬許可証を得なければなりません。
改葬許可申請を行うには、「改葬許可申請書」「埋葬(埋蔵)証明書」「受け入れ証明書」を提出する必要があります。
自治体によっては、「申請者の身分証明書写し」「死亡者の戸籍(除籍)謄本」「墓地使用許可証(永代使用許可証)」が必要になることもあるため、事前に確認しましょう。
お墓の権利者と改葬許可申請を行う人が異なる場合には、お墓の権利者の承諾書も提出します。
改葬許可証は即日交付されることはなく、3~10日後に交付されるため、余裕をもって申請しましょう。
自治体によっては郵送で改葬手続きができるところもあります。
6.僧侶に閉眼法要を依頼する
仏教信者の場合は、お墓から遺骨を取り出す前に、閉眼法要を行います。
閉眼法要とは、今の墓石から仏様の魂を抜き、墓石をもとの石に戻すために行われる法要です。
御霊抜きの法要、閉魂法要、性根抜きと呼ばれることもあります。
お坊さんにお経を上げてもらいますので、お布施を用意します。
仏教徒でない場合は、閉眼法要をする必要はありません。
しかし、閉眼法要を行っていないお墓は解体できないという石材店も多いため、法要を行わない場合にも事前確認が必要です。
法要が終わったら、石材店スタッフ立ち合いのもと、お墓から遺骨を取り出します。
7.石材店が墓石の撤去工事を行う
工事のしやすい場所にお墓があれば、工事は1日で終わります。
山地などの難所にお墓がある場合は、2~3日かけて行われることもあるようです。
撤去工事が終わったら、管理者に墓地を返還します。
8.用意しておいたお墓に遺骨を納骨する
取り出した遺骨を、用意しておいたお墓に納骨します。
納骨の際は「改葬許可証」が必要になります。
忘れずに持参しましょう。
また、改葬を終えたら、関係する方々に挨拶状を送ります。
これで、墓じまいは終わりです。
墓じまいにかかる費用
墓じまいするには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
墓じまいにかかる費用について、以下の表にまとめました。
| 費用相場 | |
| 墓石解体費用 | 20~30万円 (8~10万円/㎡) |
| 閉眼法要のお布施 | 1~5万円 |
| 離檀料(寺院墓地のみ) | 1~20万円 |
| 改葬許可証発行手数料 | 0~500円 |
| 新しいお墓の購入費用 | 10~150万 |
| 開眼法要のお布施 | 1~5万円 |
墓地の立地条件によっては、墓石解体費用が相場より高くなることもあります。
石材店に提示された工事費用が適正が判断するためにも、可能であれば複数社で相見積もりを取ることをおすすめします。
墓じまいしないでお墓を放っておくとどうなる?
ここまで述べてきたような手順を踏んで墓じまいすることを面倒だと感じる方も中にはいらっしゃるでしょう。
しかし、墓じまいしないでお墓を放っておくのは、墓地の管理者によってお墓を強制的に撤去される可能性があるのでおすすめできません。
墓地の管理者によるお墓の撤去手続きは、管理費の滞納が3年続いた時点で開始されます。
墓地の管理者は、官報や墓所に設置した立札で、お墓の使用者や被埋葬者の縁故者に対し、1年以内に申し出るよう呼びかけます。
1年以上連絡がなかった場合、お墓は無縁墳墓とみなされ、墓地の管理者はお墓の撤去と改葬手続きを行えるようになるのです。
改葬手続きを行ってお墓から取り出した遺骨は、墓地内の供養塔や無縁塚に合祀されます。
お墓の撤去・改葬費用は、墓地を管理している自治体やお寺が負担します。
自治体やお寺の財政を圧迫しないためにも、きちんと墓じまいしましょう。
墓じまいに関する注意点
墓じまいを進めるにあたり、注意すべき点を押さえましょう。
可能なら相見積もりを取る
自治体が運営する公営霊園や所有している土地が墓地になっている場合では、複数の石材店で工事費用の相見積もりを取ることができます。
見積もり金額が適正なのか判断するためにも、相見積もりを取ることがおすすめです。
しかし、民営霊園や寺院墓地では、指定された業者でなければ墓じまい工事ができないところもあります。
相見積もりを取れないこともあるため、事前に指定業者の有無を確認しましょう。
改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要
自治体によって異なりますが、遺骨の数分の改葬許可申請書が必要なケースが多いようです。
事前にお墓に何体入っているかは把握しておいたほうがよいでしょう。
自治体によっては1枚の改葬許可申請書で済む場合もあるため、役所や自治体HPにて必要書類を確認しましょう。
まとめ
墓じまいをするには、役所で「改葬許可申請書」、新しい墓地で「受け入れ証明書」、既存の墓地で「埋葬(埋蔵証明書)」、その他必要書類を発行してもらい、それらを役所に提出し「改葬許可証」を交付してもらう必要があります。
まずは必要な書類の確認と親族への相談から、墓じまいの準備を始めましょう。
墓じまいの見積もりサービスに相談してみよう
お墓さがしでは、墓じまいをパック料金で承っています。
お見積り・ご相談は完全無料ですので、お気軽にご相談ください。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
墓じまいはどのような手順で行う?必要な手続きや注意点に関する記事
-
墓じまいとは?費用と流れを詳しく解説!トラブル対策も紹介
面倒を見ることができないお墓、あるいは、将来的にお世話をする人がいなくなってしまうお墓にお悩みでしょうか?お墓と聞いてイメー…
2024年8月13日
-
永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説
こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…
2025年2月6日
-
墓じまいの手続きと必要書類がこれで分かる!手順と流れを解説
墓じまいとは、お墓を解体・撤去して墓地を管理者に返還するまでの一連の流れを言います。また、遺骨を現在のお墓から移動することを…
2023年7月19日
墓じまいの手順に関するQ&A
-
墓じまいを考えているのですが、まずは何をすればいいでしょうか。
墓じまいをするには改葬手続きをする必要があります。まずは、墓地のある自治体のHPや役所で改葬許可申請に必要な書類を確認しましょう。次に、お墓の関係者に相談し、墓じまいの了承を得ておきます。
-
改葬手続きにはどんな書類が必要ですか?
改葬許可証を得る必要があります。改葬許可申請を行うには、「改葬許可申請書」「埋葬(埋蔵)証明書」「受け入れ証明書」を自治体に提出する必要があります。自治体によっては「申請者の身分証明書写し」「死亡者の戸籍(除籍)謄本」「墓地使用許可証(永代使用許可証)」が必要になることもあるため、自治体のHP等で確認しましょう。
-
改葬許可証はすぐに交付されますか?
改葬許可証は即日交付されることはなく、3~10日後に交付されるため、余裕をもって申請しましょう。