
ペットの手元供養の方法ついて解説!おすすめのグッズも紹介
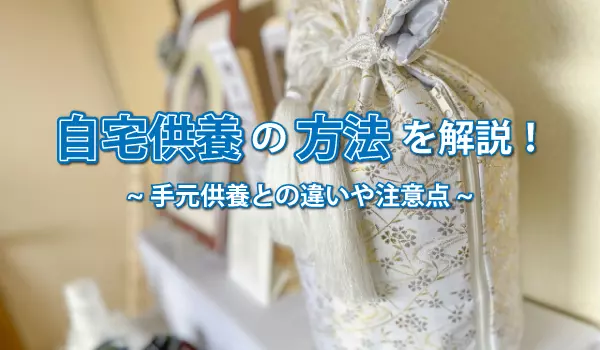
四十九日や一周忌を過ぎても、自宅に遺骨を置いたまま供養することがあります。
理由としては、故人と離れがたいなどが挙げられます。
少子化が進む現代では、お墓を建てずに自宅を供養の場とする考え方も広まっています。
今回の記事では、自宅で遺骨を安置する自宅供養について解説します。
目次
自宅供養とは、自宅に遺骨を安置して供養することをいいます。
ひとえに自宅供養といっても「骨壺のまま家に置いておく」「専用の自宅供養グッズを改めて用意する」など方法はさまざまです。
遺骨を自宅に置き続けることは違法ではありません。
お墓や遺骨については、「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、墓埋法)で定められています。
墓埋法では、行政が経営を許可した墓地以外に遺骨を埋葬することを禁止しています。
例えば、家の庭にお墓を作って遺骨を埋葬すると違法になります。
ただし、墓埋法では遺骨をいつまでに埋葬するといった期限が定められていません。
遺骨をずっと自宅で保管することによって、法規定に違反することはありません。
ペットの遺骨を自宅供養することは、法律上問題ありません。
人間と同じく、ペットの遺骨も自宅で供養できます。
ただし、自宅供養をしている遺骨は、最終的にどこかへ納骨する必要があります。
霊園の規定によってはペットの納骨が禁止されていることがあるので注意しましょう。
ペットと離れたくない方は、ペット対応の霊園を調べておくことをおすすめします。
自宅供養にはどのような方法があるのでしょうか。
ここでは、自宅供養のパターンを3つ紹介します。
1つ目は、骨壺のまま安置する方法です。
遺骨の置き場所は、仏間や仏壇の近くなどが挙げられます。
仏間が無い場合は、リビングや寝室、クローゼットなどに置く方が多いようです。
骨壺は寒暖差で結露すると内部に水がたまるので、直射日光の当たらない場所に保管しましょう。
また、ごくたまにカビが生えることもあるので、湿気がたまりやすい押し入れ、水回りには置かないようにします。
2つ目は、後飾り祭壇を供養壇にする方法です。
後飾り祭壇とは、命日から四十九日まで自宅に置いておく祭壇です。
通常、後飾り祭壇は四十九日を目処に処分され、遺骨はお墓に納骨、白木位牌は処分して本位牌を仏壇に置きます。
ただし、後飾り祭壇を一定期間後までに処分しないと違法になるということはありません。
後飾り祭壇をそのまま遺骨の供養場所として残しておいても良いでしょう。
3つ目は、自宅供養用に遺骨を収納できる仏壇を購入するという方法です。
仏壇の下部に収骨用の引き出しがついており、全骨収納できるものもあります。
遺骨の収納には、場合によって粉骨が必要になることもあります。
普段は目につかないところに遺骨をしまうので、来客などがあった際も違和感なく自宅供養ができます。
また、サイズも台付きのものから家具の上に置ける上置き仏壇など好みに合わせることができます。
近年に誕生した仏壇ですので、デザインは洋風なものが多いようです。
自宅供養と手元供養の違いは、分骨をするかどうかです。
分骨とはご遺骨を2か所以上に分けて供養することをいい、遺骨の一部を自宅や手元で保管することを手元供養といいます。
遺骨をすべて残す自宅供養とは異なる意味合いがあります。
手元供養にはどのような方法があるのでしょうか。
ここでは、手元供養の方法を3つ紹介します。

インテリアのようなデザインに製作されており、リビングにおいても違和感がありません。

水晶のようなデザインや、文字を入れて位牌のように加工してくれるものなどがあります。

遺骨をアクセサリーにする場合は、遺骨を小さな入れ物に収納するタイプと、宝石などに加工したものを使用するタイプがあります。

ここでは、自宅供養のメリットを3つ解説します。
自宅供養をしていれば、お墓まで行かなくても毎日お参りができます。
仮にお墓を作ったとすると、お墓参りの機会は命日やお盆など限られたタイミングになるでしょう。
自宅に遺骨があれば、時間や天候などに囚われず、いつでも手を合わせることができます。
自宅供養をすれば、お墓の購入費用を抑えられます。
お墓を建てる場合は、おおよそ100万円程度の費用が必要です。
樹木葬や納骨堂の場合も、人数や種類によりますが30~100万円程度が相場です。
自宅供養の場合は、これらの費用を軽減できます。
自宅供養にすればお墓を持たなくていいので、お墓の負担を子どもに残すこともありません。
一般的な墓石のお墓を持った場合は、お墓の手入れや年間管理費の支払いなど、後の代に負担がかかります。
自宅供養であれば、跡継ぎに負担をかけずに自分で供養できます。
ただし、供養する方が亡くなった場合は、遺骨をどこかに納める必要があります。
供養する方が亡くなった時に備えて、最終的な納骨先は決めておきましょう。
自宅供養をするにあたって、覚えておくべき注意点を3つ紹介します。
火葬された直後の遺骨は完全に滅菌状態で、そのまま骨壺に入れられます。
遺骨は湿気やカビ菌に弱いため、保管の状態が悪いと遺骨にカビが生えます。
保管の際は、以下に注意しましょう。
自宅供養していた人が亡くなった時は、残された人が供養する必要があります。
後の負担を考えて、自宅供養の期限と納骨先を決めておきましょう。
自宅供養の期限は、33回忌や50回忌が終わったタイミングや供養する本人が亡くなった時などが挙げられます。
納骨先は、家族のお墓があればそこに埋葬すればいいでしょう。
家のお墓がない・お墓の跡継ぎがいないという方は、永代供養墓を検討しましょう。
永代供養墓とは、墓地の管理者や住職が永代にわたり供養をしてくれるお墓です。
承継者を必要としないため、どなたでも安心して利用できます。
親戚や身内の考え方次第では、納骨しないことに反対されることがあるでしょう。
自宅供養に反対する理由は、「納骨しないと成仏できない」などが挙げられます。
しかし、仏教の教義上では、納骨に関係なく四十九日の時点で閻魔大王の裁きを受け次の転生先が決まります。
納骨しないことを理由に、故人の魂がこの世をさまよい続けることはありません。
ただし、遺骨が身近にあることに恐怖を感じる方や、遺骨が見える場所にあることで悲しみを引きずってしまう方もいます。
少なくとも、自宅供養に関しては一緒に暮らすご家族の同意を得ましょう。
自宅供養に関して、以下の内容を紹介してきました。
最近では、自宅供養の仏壇などのグッズも販売されています。
自宅供養を考えている方は、ぜひ一度ご検討ください。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
遺骨アクセサリーや遺骨の加工品は、手元供養品の一つとして普及しています。今回は、遺骨アクセサリーを始めとする遺骨の加工品につ…
2024年6月3日
こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…
2025年2月6日
亡くなっても大切な人と離れがたく、納骨をせずに、遺骨を自宅に安置したいという方も少なくありません。この記事では、自宅で遺骨を…
2024年6月4日
自宅供養とは、自宅に遺骨を安置して供養することをいいます。自宅供養の方法は、「骨壺のまま安置する」「後飾り祭壇を使い続ける」「収骨できる仏壇を購入する」などが挙げられます。
「遺骨にカビが生えることがある」「最終的にどこかへ納骨しなければならない」「身内や親戚に納骨を迫られることがある」という点に注意しましょう。
自宅供養は「全ての遺骨を自宅に安置すること」手元供養は「遺骨を分骨して供養すること」をいいます。