納骨堂を決めるには、現地見学が重要です。従来のような墓石を建てる墓地とは雰囲気やお参りの方法も異なり、行ってみて初めて分かることもたくさんあります。
しかし、基本的に何度も納骨堂を契約することはないので、「どこに気をつけて見学するべきか」「何を聞いておくべきなのか」はいまいち分からないかもしれません。
今回の記事では、納骨堂を見学するまでの流れや、見学をする際のチェックポイントなどを紹介します。
記事のポイント

条件に合う納骨堂を探してみる >>
納骨堂とは
納骨堂とは、遺骨を屋内に安置する施設です。
かつては遺骨の一時預かり施設として利用されていましたが、「屋内のお墓」「承継不要のお墓」として広く販売されています。
お墓として利用できる納骨堂が増えるにつれてその形態も様々になり、種類によって使い勝手や納骨できる人数などが変わります。
納骨堂の見学に行くまでの流れ
納骨堂の見学に行くにはどうすればいいでしょうか?見学までの流れを解説します。
納骨堂の見学に行くまでの流れ
1.見学する納骨堂を探す
2.見学予約を取る
3.現地に行く
1.見学する納骨堂を探す
まずは、どの納骨堂の見学をするかを決めましょう。
以下のような条件を考えていくと、自ずと該当する納骨堂も絞られてきます。
納骨堂選びで考える条件の例
- エリア・アクセス
- 価格
- 使用する人数
- 使用できる宗教・宗派
「お墓さがし」では全国の納骨堂をご紹介しています。
こちらから、条件に合う納骨堂を探してみましょう。
条件に合う納骨堂を探してみる >>
2.見学予約を取る
見学する納骨堂を決めたら、「見学予約」を取ります。予約は必ず取ることをおすすめします。
予約をしないで行ってしまうと、現地の担当者の手が塞がっていて案内を受けられないことがあります。
中を見るだけと思っても、担当者が付いていないと区画の中や施設などが見られないこともあります。
また、普通のお墓にはない制度があることも多く、例えば、「区画の使用期間が限られている」「8名まで納骨できるが、3名以上の場合は粉骨(遺骨を粉状に砕くこと)が必要」のようなものです。納骨堂選びにはこうした制度の内容も重要なので、やはり担当者から直接説明を受けることを強くおすすめします。
「お墓さがし」では、全国の納骨堂の見学予約も受け付けています。
ぜひご活用ください。
条件に合う納骨堂を探してみる >>
3.現地に行く
決定した日時で現地に行きます。
お車の方は、事前に駐車場があるか確認しておきましょう。
見学に行く前の下準備
見学に行く前に、あらかじめ気になっていることをまとめておくと、その後がスムーズです。
各人の要望や家族の事情によって気になることは変わりますが、例えば、以下のようなことはどうでしょうか。
宗教について
- 戒名はなくても良いか
- 仏教以外の宗教の人も納骨できるか
- 宗教が違う者同士の納骨はできるか
- 苗字が違う者同士の納骨はできるか
- 他寺など他所の宗教者を同伴してもいいか
- 葬儀は納骨堂を管理するお寺に頼むことが必須か
- 納骨法要は必須か
- 納骨後の回忌法要は必須か
- 寄付などを頼まれることはあるか
区画・納骨について
- 承継者が居なくても利用できるか
- 何人まで納骨できるか
- 納骨する予定の人を後から増やすことはできるか
- 他のお墓から取り出した遺骨を納骨できるか
- 区画はいつまで使用できるか
- ペットは納骨できるか
- 遺骨と一緒に位牌も安置できるか
施設について
- 駐車場は使えるか
- 納骨堂の中に葬儀や法要、会食の施設はあるか
- 納骨まで遺骨を預かってもらうことはできるか
見学で確認したいチェックポイント4つ
見学で確認したいチェックポイント
- 現地までのアクセスや道のりはどうか
- スタッフや住職の対応はどうか
- 清掃や手入れはきちんとされているか
- お参りやお供えはどうなるか
現地に付いたら、参拝エリアや納骨する区画、施設などを案内してもらえます。
見学で確認したいチェックポイントを紹介します。
1.現地までのアクセスや道のりはどうか
見学は、実際にお参りをするときと同じ交通手段で行くことをおすすめします。
例えば、駅から徒歩3分であっても、平坦な道なのか坂があるのかでアクセスのしやすさが変わります。
他にも、バス停が近いがバスの本数は十分か、車でお参りに行くなら駐車場の広さや停めやすさはどうか、など、実際に行ってみて分かることがあるかもしれません。
今後、定期的にお参りに行くことを想像して、無理なくアクセスできるかを考えてみましょう。
2.スタッフや住職の対応はどうか
現地で案内をしてくれるスタッフの対応や、納骨堂を運営するお寺の住職のお話も、納骨堂を選ぶ際のポイントになります。
納骨堂を契約すれば、その先の付き合いも長くなります。
初見で信用に足る相手かを見極めることは簡単ではありませんが、逆にそのわずかな機会で不信感を持つようであれば、他の納骨堂も検討することをおすすめします。
3.清掃や手入れはきちんとされているか
納骨堂内の清掃や手入れが行き届いているか、確認しましょう。
きちんと手入れされているかどうかは利用時の快適さに関わるばかりでなく、管理コストを正しくかけているかの指標にもなります。
4.お参りやお供えはどうなるか
お参りの方法は、見学の過程で説明してもらえるはずです。
お参りやお供えの方法は、納骨堂によって異なり、遺骨を前に個別で手を合わせられるところ、共用の供物台にお供えをするところ、ロウソクや線香などの火気が利用できないところ、仏具などを備えておくことができるところなど、様々な特色があります。
どのような形で故人を偲びたいか、しっくりくるところを選びましょう。
現地で聞いておきたい質問
見学をする際は、現地のスタッフが案内してくれます。
見学でスタッフに聞いておきたい質問を紹介します。
購入価格と維持費
購入価格はいくらか、契約以降にかかる費用はいくらかを確認しましょう。
「契約以降にかかる費用」は、例えば以下のようなものが考えられます。
契約後にかかる可能性がある費用の例
- 年間管理費(年間護持費)
- 納骨手数料・納骨法要のお布施
- 新たに納骨した人の分の永代供養料
など
いずれも必ずしもかかる費用ではなく、必要な費用は納骨堂によります。
「永代供養料」は、契約時に支払えばそれ以降はかからない場合と、納骨する人数が増えたときに改めて支払う場合があります。
宗教や法要などの制限
納骨堂を使用できる宗教や宗旨・宗派について確認しましょう。
「使用者の宗派不問」としていても、「在来仏教に限る」などの要件がつくことがあります。
キリスト教や神道、新宗教の方など、在来仏教以外の信仰がある方は必ず確認しましょう。
また、「納骨時には必ず納骨法要をする」「他所の宗教者は同伴できない」などのルールが設けられていることもあります。
なお、ほとんどの納骨堂では、区画の使用期限が過ぎた遺骨は「合祀墓」に移動され、その後に定期的な法要によって供養されます。
読経されたくないという方は、公益法人や自治体が運営する納骨堂を探してみましょう。
区画の使用人数と使用期間
区画は何人でいつまで利用できるかについて確認しましょう。
納骨堂では一定期間後、遺骨を個別区画から「合祀墓」に移動して供養することが一般的です。
「合祀墓」とは、不特定多数の遺骨を一つの納骨室に埋葬し、供養するお墓です。
「一定期間」がどの程度かは納骨堂やプランにより、「契約時から50年間」「最後の納骨から十三回忌」「年間管理費を納める限り」など様々に設定されます。
また、「2人までは骨壺で、それ以上の人数で利用するなら粉骨(遺骨をパウダー状に砕くこと)が必要」など、遺骨の取り扱いも変わることがあります。
見学はした方が良い?
納骨堂を契約する前に、見学は必ず行きましょう。
これまで述べてきたように、アクセスのしやすさや手入れ行き届いているか、その場の雰囲気など、行ってみなければ分からないことはたくさんあります。
一般的に、納骨堂を含めるお墓は、支払い後の使用料の返金はしてもらえません。
納骨堂は長く使うものですから、特段の事情がなければ、後悔しないよう、必ず現地を一度見学しましょう。
見学した後の流れ
見学をしてから、納骨までの流れを紹介します。
納骨堂の見学から納骨までの流れ
1.納骨堂見学
2.比較・検討
3.契約・入金
4.納骨
1.納骨堂見学
実際に現地に赴き、お参りのしやすさや雰囲気などを体感しましょう。
スタッフが案内してくれるので、気になるところは聞いておきます。
一つで決まりきらなければ、他の納骨堂を見学するのも良いでしょう。
2.比較・検討
見学した納骨堂を比較して、どこが良いかを決めます。
見学の際にはスタッフの名刺をもらうはずなので、後々に気になったところがあれば問い合わせます。
3.契約・入金
納骨堂を決めたら、名刺の連絡先に問い合わせ、契約したい旨を伝えます。
契約書の取り交わしや入金など、段取りを決めて契約します。
4.納骨
すでに遺骨がある場合は、契約した区画に納骨します。
納骨式の有無や段取りなどを現地のスタッフやお寺と相談して決めます。
決定した日時で遺骨を納骨堂に持参し、納骨します。
参考:納骨堂の見学レポート
「お墓さがし」では、納骨堂の見学レポートも掲載しています。
気になっている納骨堂があれば、ぜひご覧ください。
まとめ
納骨堂はこれまでの墓石のお墓とは異なる点が多く、行ってみて初めて分かることがたくさんあります。必ず検討段階で見学に行きましょう。また、確実に担当者に案内してもらうためにも、見学には予約が必須です。
見学では、「アクセスのしやすさや」「スタッフの対応」「手入れや管理の様子」「お参りの方法」はチェックしておきます。
この他、費用や宗教の条件、区画のシステムなどの説明もしてもらいましょう。
納骨堂をお探しですか?
お墓さがしでは、全国にある納骨堂を掲載しています。
ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。

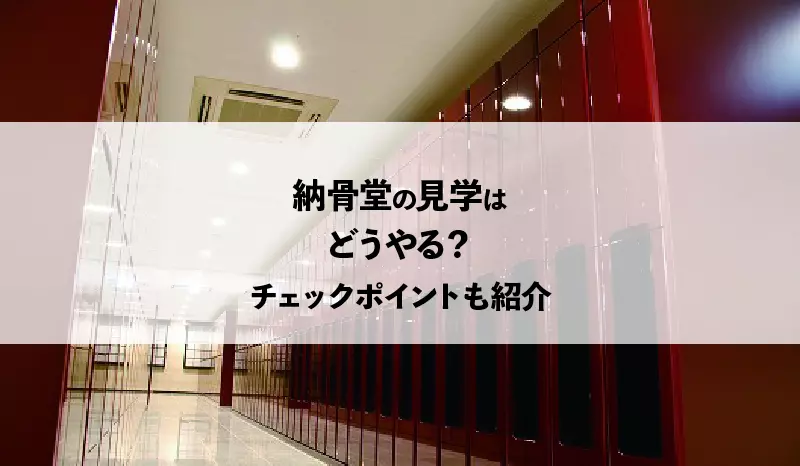






経歴
2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。